ベルリンを拠点に、彫刻とダンスを主な表現形式として作品制作を行ない、展覧会や舞台公演を横断しながら作品を発表している谷中佑輔の美術館初個展。


ベルリンを拠点に、彫刻とダンスを主な表現形式として作品制作を行ない、展覧会や舞台公演を横断しながら作品を発表している谷中佑輔の美術館初個展。
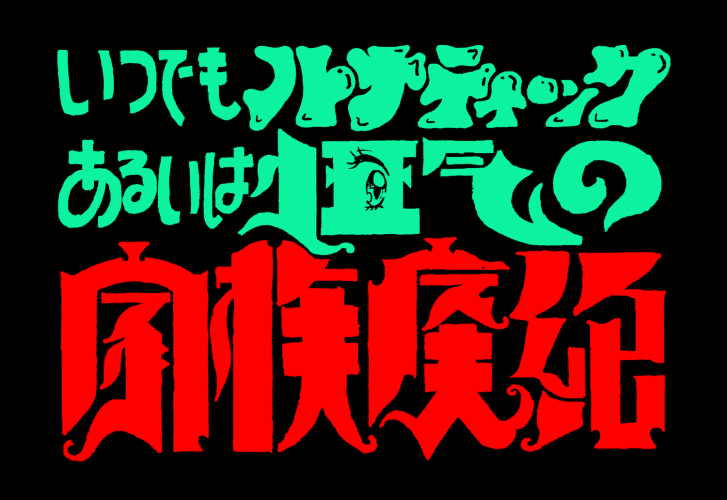
αMプロジェクト2023‒2024「開発の再開発」の最終回となる8番目の展覧会として、遠藤麻衣と丸山美佳によるコレクティブ、Multiple Spiritsの展覧会を開催。ジンや雑誌が複数の筆者による寄稿で構成されるように、マルスピのほかに複数のアーティストが参加する。

ガザ出身のパレスチナ人映像作家・写真家のアメル・ナーセルの日本初の写真展「GAZA. Signal of Life」が東京藝術大学音楽学部キャンパス 大学会館2階 展示室で開催。

リニューアル・オープン後初の展覧会となる本展では、同館のコレクションそして展覧会活動の核をなすアンリ・ド・トゥールーズ゠ロートレックの作品に改めて注目し、ソフィ・カルとの協働を通じて、美術館活動に新たな視点を取り込み、今後の発展に繋げていくことを目指す。

東京都現代美術館での個展「柔らかな舞台」も記憶に新しい、20年以上にわたり国際的に活動してきたオランダの現代美術を代表するアーティスト、ウェンデリン・ファン・オルデンボルフの新作個展を開催。1930年代から50年代にかけて日本、オランダ、インドネシアで活躍した女性たちに着想した新作などを発表。

鉄を用いて空間に線を描くような彫刻で表現の地平を切り拓いてきた青木野枝と、無色透明のガラス作品を通して場のエネルギーを掬い取り光に変換してきた三嶋りつ惠の二人展。

神奈川・相模原市と東京都町田市・八王子市の一部に拠点を置くスタジオが同時期にオープンスタジオを実施するアートプロジェクト「SUPER OPEN STUDIO (S.O.S.)」が、2024年11月9日、10日、11日、16日、17日の5日間にわたり開催。

2024年11月7日から10日の4日間にわたり、東京における現代美術の創造性と多様性を国内外に発信するアートイベント「アートウィーク東京」が開催。独自のプログラムや新しい試みも多数。

展示・音楽・パフォーマンスなど、のべ65組が参加する回遊型オールナイトアートイベント「BENTEN 2024」が、歌舞伎町界隈一帯で初開催。Chim↑Pom from Smappa!Groupが芸術監督を務め、独自の芸術地区として成立していることを可視化する。
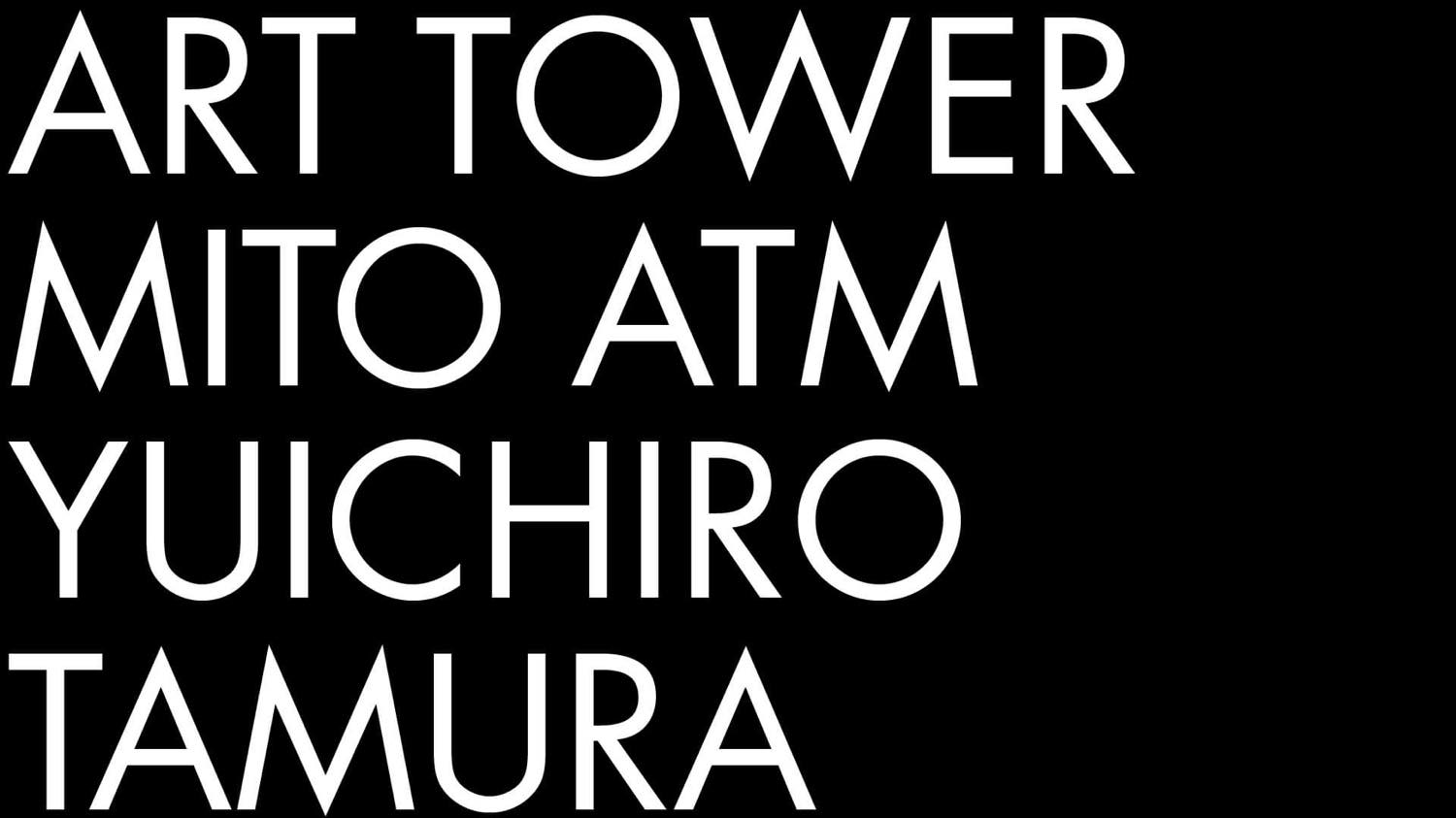
ナレーションや語り手を伴った物語、説話、エピソードのような形態で、ナラティヴな要素をもつ作品を構築してきた田村友一郎の過去最大規模の個展。制作の出発点であるテキストの述作を生成AIに委ねた新作インスタレーション《ATM》を発表。

11月29日より、世界有数の舞台芸術プラットフォームとして、同時代の舞台芸術に取り組む国内外のプロフェッショナルの交流の場として知られるYPAM2024が開幕。YPAMディレクションでは、ユニ・ホン・シャープ、ナム・ファヨン、オン・ケンセンらの作品を紹介。

ラテックス製のボディースーツで自身の身体を拡張させて家畜等のキャラクターに扮したパフォーマンスで知られるサエボーグの個展。農場が舞台の中心となった複数の過去作品を再構築し、表題作となる新作インスタレーション作品《Enchanted Animals》を発表する。