関東大震災から100年となる本年、多くの関連報道や論評が世に出るなか、筆者は一見するとそこには直結しない——しかし誰もがよく知る存在をめぐる展覧会を訪ねた。


関東大震災から100年となる本年、多くの関連報道や論評が世に出るなか、筆者は一見するとそこには直結しない——しかし誰もがよく知る存在をめぐる展覧会を訪ねた。

現代中国の文学や芸術を研究する牧陽一責任編集による「艾未未のことば」。今回は台湾国際放送(Rti)で放映されたインタビューを翻訳掲載。天安門事件で学生指導者を務めた民主運動家ウーアルカイシを聞き手に、艾未未が自由や抵抗をテーマに人生を振り返る。

ドクメンタ15を断念した美術批評家の杉田敦は、ホドロジーという研究姿勢を確認しつつ、コソヴォ共和国の首都プリシュティナで開かれたマニフェスタに向かう。マニフェスタに関する考察を通じて見えてきたものとは。

新型コロナ禍から約3年。マスク着用方針の見直しなどが進むなか、筆者はこの間の動きを、一見するとつながりの薄い12年前の福島原発事故との関係から考察する。昨秋と今春の福島訪問で感じた「熱源」をめぐる論考。
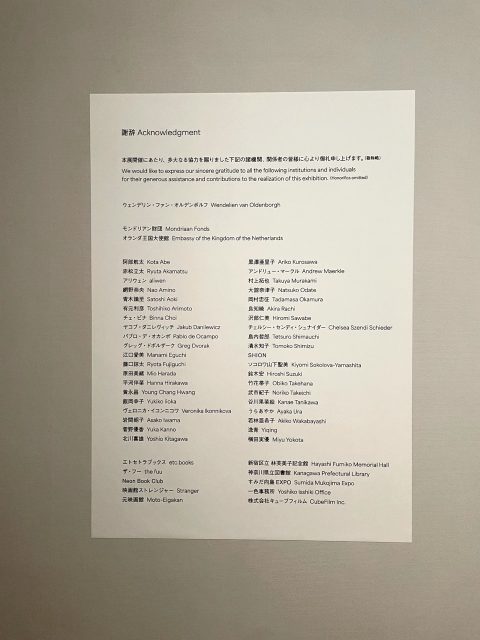
映像メディア学研究者の馬定延との往復書簡。締めくくりとなる田中からの手紙は、「公」開の「私」信ともいうべきこのやりとりに可能性を託しつつ、映像をめぐる馬さんからの問いに応える。

2018年に亡くなった小杉武久の表現について、彼の他界後も続く関連企画を通じて改めて論考する。またその延長線上に、小杉と親交のあった和泉希洋志のスパイスカレー店での営みをひとつの表現活動としてとらえる。

ドクメンタを訪れるべきか訪れないべきか。継続してきた経験を手放し、異なる経路を選んだ杉田は、立ち止まり、時に過去を振り返りながら、ドクメンタを巡る別様の考察を進める。

映像メディア学研究者の馬定延との往復書簡。馬からの最後の手紙は、作品における「出来事とその記録」の関係性をめぐり、作家、キュレーター、参加者、観衆の関係性をふまえ、そこで開かれ得る可能性を問う。

シュウゾウ・アヅチ・ガリバー「消息の将来」展に際し、あるパフォーマンスの「新しい解釈による再演」が行われた。筆者は1枚のハンドアウトから初演時の状況を考察し、再演を見つめながら作家の本質に迫る。

世界文化賞授賞式のために来日した艾未未が、埼玉大学で学生との対話を行なった。美術館での活動のみならず、「対話」もまた重要な作品と捉える艾未未がさまざまな質問に答える。

映像メディア学研究者の馬定延さんとの往復書簡。田中からの二通目の手紙は、ベルリンでの最新プロジェクト(イベント)を紹介しながら、映像の「展示」と「上映」をめぐるある視点について綴る。

この夏に東京で開催された川内の個展をめぐり、筆者はプラトンの中期対話篇のひとつを引きつつ、自身にとっての「批評という実践」のありかたも見つめながら論考する。