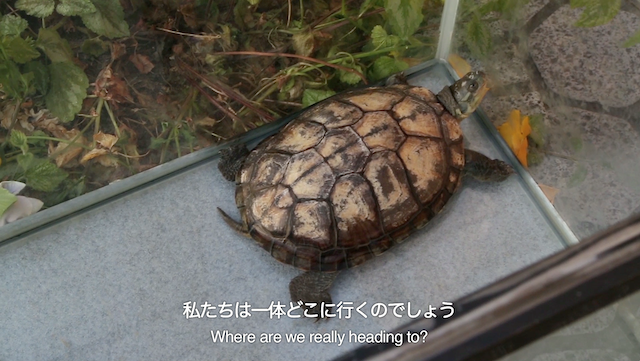 All images:百瀬文 x イム・フンスン『交換日記』
All images:百瀬文 x イム・フンスン『交換日記』
フーガの技法|百瀬文+イム・フンスン《交換日記》を見る
文 / 林卓行
出だしはいかにもたどたどしい。ナレーションの声は訥弁というよりは語る意志にとぼしく聞こえ、それによって綴られてゆく詩的なフレーズには、弛緩した常套句=クリシェも混じる。
2015年に催された日韓共同の現代作家展、『アーティスト・ファイル 2015 隣の部屋』(国立新美術館、東京)にさいし、おなじ映像のアーティストとしてなにか共同制作をというイムの呼びかけに、百瀬はこの《交換日記》という企図で応じた。それぞれが自分のいる場所で撮影した映像素材を相手に送り、送られた相手はそれを自由に編集、さらに自身によるナレーションを重ねて、一編の映像に仕上げてゆく。そしてこの一連の過程を、ふたりで交互に立場を入れ替えながら繰り返す、というのがその企ての内容だ。このとき、「往復書簡」のような単純な選択を避けたことには、「身体とことば」とか「公と私」の境界をたくみにすくいとると評される百瀬らしい、ある種の機知あるいは屈曲もうかがえる。
だがこの試みをどう切り出すか、つまり最初の一編をどちらが、どのように示すかというのは難題だ。いわゆる「交換日記」がすでにして持つ倒錯を、つまり「日記」は自分を宛先にするが、それをたがいに「交換」するとは、その宛先として他人を持つことになるという倒錯を、さらに変形を加えられたこの枠組みのなかで、どう扱うか。第一編で百瀬は果敢にこの難題を引き受けるが、イムの映像に重ねられた彼女のナラティヴ/ナレーションの内容は、その倒錯をついにさばききれないままに、あるいは両義的にとどめておくこともできないままに、相手を宛先にして「おやすみなさい」と呟いてしまうことで終わる。それでは「往復書簡」と変わるところがない。
《交換日記》としての歯車が本格的に回りはじめるのは、第二編、百瀬の送った映像素材を、イムが編集してナラティヴにする/ナレーションするところからだ。彼は百瀬から送られてきた映像から一匹の亀を取り上げ、それを鍵のひとつに、自身の出自を語りはじめる。圧倒的なリアリティをもって語られるその話題の、しかし真偽を確認する方法は、じつは作品を見るわたしたち観客の手には与えられてない(もちろんたんにそれが事実だということは、わたしたちのこの不可能性と別個にありうる)。それでも、百瀬がたまたま撮影した亀がイムに自身の出自を思い出させたのだという偶然とあわせて、わたしたち観客はイムの話が真であることを信じたくなる。つまり、イムが語る出自のエピソードにリアリティを与えているのは、イムのナラティヴ/ナレーションの内容でもなければ、もちろん元の文脈をまったく無視して取り出されてきて、イムの声に重なる映像でもない。百瀬による亀の映像に、イムによる出自の語りを重ねさせている、この《交換日記》全体の枠組みそのものなのである。
イムはさらに第一編の百瀬のナレーションからも、その出自の物語を構成する、重要な要素を引き出しているように見える。第一編の百瀬は、黒猫と美術館の壁という(それ自体は残念ながらこの種の独白にありふれた)ふたつの要素のあいだに、直立したまま壁に塗り込められる、小説『黒猫』(E・A・ポー)中の女性の死体の話題を置いていた。いっぽう第二編のイムのナレーションでは、亡くなった祖母が納められた棺のようす、つまり狭い地下から運び出すにさいして、それをほとんど直立させなければならなかったという逸話が語られる。そのとき、イムの祖母の亡骸のリアリティを支えているのもまた『黒猫』中の死体の描写であり、さらにはその描写を呼び込んだ、この《交換日記》全体なのである。
ここからは雪崩打つように、と言ってよい。ディテールの水準でいうなら、第二編でイムがそのナラティヴの構成上でさりげなく観客に注視をうながす、若い女性がリズミカルに踏み鳴らす脚を車窓越しに百瀬のカメラがとらえた映像は、そのまま第三編でこんどは百瀬のナラティヴによって、イム撮影の衣料品店のディスプレイに用いられた動くマネキンの脚として、変奏されることになる。あるいは百瀬による映像にいかにも直截に登場していた一匹の蛭は、つぎの登場では百瀬のナラティヴ/ナレーションのなかで、「蛭のように」と比喩を担うものとして語られる。



より大きな主題の水準でいうなら、この第三編の冒頭、百瀬にもわかるだろう漢字による記録を確認しながら、百瀬にはわからない韓国語で過去を語る老女がとりわけ重要だ。彼女の映像を背景に、百瀬はだれにでも読み書きできる普遍言語エスペラントを夢見た男、ザメンホフのエピソードを語る。そしてこの老女はその後、イムのナラティヴ/ナレーションによって「思い出したからってなんになる」という痛切な声のあるじとして(だがそう語る彼女のその姿もその声も、そのときスクリーンにある百瀬による映像には登場しない)、また百瀬のナラティヴ/ナレーションの語る「山羊たちに置き換えられただろう体」のあるじとして(こちらではイムの撮影した老女の映像が断片的に挿入される)、などなどと、何回かにわたって変奏されてゆくことになるだろう。そしてその変奏と変奏のあいだには、百瀬の声による(だからイムの映像に登場しない)、兵士に性的な奉仕を強いられた女性が仰ぎ見ただろう月を歌った詩の朗読、そして百瀬が撮影した(だからイムのナラティヴ/ナレーションには登場しない)、駅頭のテレビごと画面内に映る「従軍慰安婦問題」を報じる映像が、それぞれ挿入される。かつて老女を襲っただろう戦時下における性暴力という主題は、こうして繰り返し変奏され、また詩や映像の引用と組み合わされることによって、切れ切れでありながらくっきりとした輪郭を与えられてゆくのだ。
はじめのうち散漫にちりばめられたモティーフが、やがてイムと百瀬というふたりの作者の手のうちを、そしてそれぞれにイメージ=映像とナラティヴ=語りという二重になった平行線上をたがいに追いかけ合い、あるいはときにそれらの線を自在にまたぎながら、繰り返し変奏されてゆくことで進行する。それがこの《交換日記》の本性である。そこにはすでに二分法の確立と同時にその解体があるが、さらにふたりはその進行に対して、二分法に収まらない要素も積極的に組み込んでゆくだろう。日韓の対話と思われたその映像中には、ふたりがそれぞれの出身国を離れてそのとき訪れていた「第三国」として、ロンドンやモンゴル、ニューヨーク、あるいはミュンスターと言った街々が映し出される。またイムの撮影による、テムズ川を行く観光船から見上げた橋の裏側を這う鉄骨、そして橋上から真下に視線を落とすときに見える貨物船の荷物が織りなすグリッドは、鮮やかな対称性をその映像の進行中に示す(この場面にかぎらないが、本作がきわめて魅力的に描き出す細部のひとつは、やはり作中にわずかに登場する撮影者の影である)。だが百瀬はその途中にまたべつの定速移動の表象として、街並みのつくる水平線と並行に流れる、モノレールの車窓からの風景を持ち込むだろう。夕暮れ、ソウルの広場に集った群衆を慰撫する甘いメロディは、蒸し暑い東京の夜、官邸前に響く政権糾弾の怒号とこれもすぐれて対称をなすだろうが、ニューヨークでのそれを呼び水にソウルでも行われる性的少数者によるパレードは、このメロディと怒号のあいだで、(つかのま)解放の歓びを爆発させるだろう。
おずおずと内省的に、また即興的な音合わせから始めるほかなかった《交換日記》は、こうしてその進行につれて、文字通り息詰まるような緊迫感を伴う、堅固なかたちをとりはじめる。映像も声も、そしてそれによって扱われる主題のトーンも一定のままに、である。ただ弱々しかっただけの声が、声量はそのままに、訥弁としてひとつの力をともないはじめる。亀や蛭、鮑のような小動物やひとびとのなにげないしぐさ、山中や市街地の俯瞰映像といったモティーフもまたそのなかで、強い喚起力を持つものとして現れはじめるだろう。それはこの《交換日記》が、2(イム/百瀬)×2(イメージ/ナラティヴ)と合計4つの声部を自由に用いながら、そしてこの2×2のマトリクスにおさまらない第三項としての要素をもたくみに織りまぜながら、いくつものモティーフを反復、展開させてゆく、対位法を用いたフーガの技法=アートによっているからである。
ーーーーーー
ひとつ、ほんとうの蛇足を。わたしたちはいまこうして、2015年という平時からの弱々しい声が、ひとつの明確な技法=アートを経て、力強く聞こえてくるのを耳にすることができる。だが(いつでも)「いまは緊急時なのだ」と叫ぶはじめから勇ましいことばは、いつまでも荒々しいうねりのままであることを賞賛されるとき、いったいいつの時代まで届くことができるだろうか。


百瀬文 x イム・フンスン『交換日記』
2019年9月3日(火)19:30 ※百瀬文とイム・フンスンのトークイベント付き
2019年9月28日(土)- 10月4日(金)21:10-
シアター・イメージフォーラム
http://www.imageforum.co.jp/theatre/movies/2888/
林卓行|Takayuki Hayashi
1969年東京生まれ。美術批評・現代芸術論。東京藝術大学美術学部芸術学科准教授。1997年東京藝術大学美術研究科博士課程在学満期退学(美学)。主な著作に『ウォーホル(西洋絵画の巨匠9)』(小学館、2006年)、『田中功起「質問する その1(2009-2013)」』(共同執筆、ART iT、2013年)、『芸術教養シリーズ7 欧米のモダニズムとその後の運動 近現代の芸術史 造形篇I』(共著、京都造形芸術大学藝術学舎、2013年)ほか。
