第1回 展覧会という作法を乗り切るために(2) 田中さんの第1信はこちら|往復書簡 田中功起 目次 田中功起様 お便り拝読いたしました。田中さんは今ロスですか? それともどこか別の場所を飛び回っておられるのか? 今私は、沖縄のビーチで波の音を聞きながらこのメールを書いています……View More >
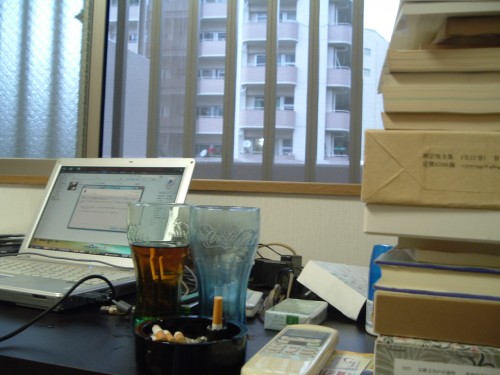
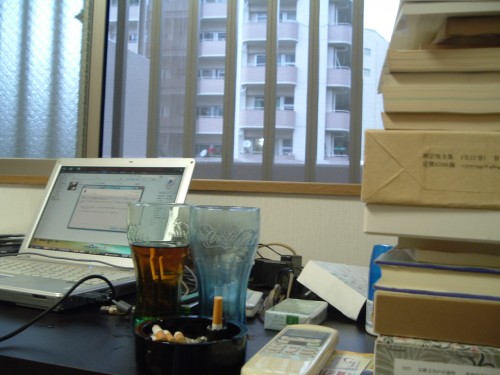
第1回 展覧会という作法を乗り切るために(2) 田中さんの第1信はこちら|往復書簡 田中功起 目次 田中功起様 お便り拝読いたしました。田中さんは今ロスですか? それともどこか別の場所を飛び回っておられるのか? 今私は、沖縄のビーチで波の音を聞きながらこのメールを書いています……View More >

日本的アートとは?:作品の価値はいかにして作られるか 前編はこちら 海外の美術作品を観ていると、セオリーで固められすぎていてつまらないんですね。 小崎 そういったシステムの問題の一方で、出品されている作品のコンセプトについて言えば、いわゆる欧米のスタンダードなアートとは離れた、非View More >

今月から月評が始まることになった。いま、その初回の原稿を書こうと机に向かったところだ。月にひとつの展覧会レビューなら『美術手帖』誌で書いているので、ここでは別のかたちを探ってみようと思う。1本に絞るのではなく、複数の展覧会や事象について書くことになるだろう。が、いっそ生活するなかView More >
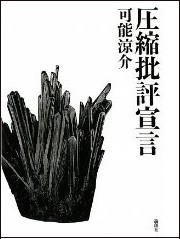
大竹伸朗の現在はどこにあるのか 今月から月評が始まることになった。いま、その初回の原稿を書こうと机に向かったところだ。月にひとつの展覧会レビューなら『美術手帖』誌で書いているので、ここでは別のかたちを探ってみようと思う。1本に絞るのではなく、複数の展覧会や事象について書くことになView More >

国際的に活躍する気鋭のアーティストが、アートをめぐる諸問題について友人知己と交わす往復書簡。ものづくりの現場で生まれる疑問を言葉にして、その言葉を他者へ投げ、投げ返される別の言葉を待つ……。第1回の相手は、批評家の土屋誠一さん。2ヶ月の間にそれぞれ2通の手紙で、現代美術の制度につView More >
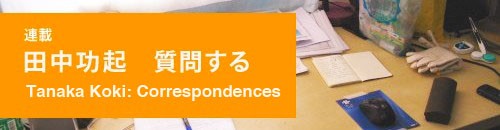
国際的に活躍する気鋭のアーティストが、アートをめぐる諸問題について友人知己と交わす往復書簡。ものづくりの現場で生まれる疑問を言葉にして、その言葉を他者へ投げ、投げ返される別の言葉を待つ……。 第18回 馬定延さんと アーティストへの質問、あるいは「これまで」と「これView More >

日本的アートとは?:作品の価値はいかにして作られるか 海外のアートフェアへいち早く進出し、村上隆、奈良美智など、世界的に著名な日本人アーティストを輩出。日本のアートマーケットの拡充に尽力するトップギャラリストと、欧米と日本における市場や作品の違いについて語り合った。 構成:編集部View More >

「日本的アートとは?」:素材と技術とアートの関係 前編はこちら 海外の作家に「ここの技術だったら依頼したい」と言ってもらえるような、現代美術の制作に特化したプロダクションも組織してみたい。 小崎 一昨年の「ミュンスター彫刻プロジェクト」で話題になった作品のひとつに、マーク・ウView More >

日本的アートとは?:素材と技術とアートの関係 国際的に活動する若手作家の筆頭格である名和晃平の作品には、既存の作品にはあまり見られない、新たな素材や技法が駆使されている。現在京都で活動する作家の、その制作態度の原点を探る。 構成:編集部 協力:小島三佳、後藤あゆみ(バンタンデザイView More >

日本的アートとは? 前編はこちら アートと名付けられるか名付けられないかを気にしないっていうことを率先してできるのは、いま、日本のような気がします。 会田 文脈ということで言えば、僕も美術史を参照したり、典型的な現代美術家のやり方をしているので、ある意味では正統派ではないかと思いView More >

日本的アートとは? 現代アートの起源は、いうまでもなく欧米にある。では、日本などの非欧米圏において、現代アートの作品を作る、あるいは観るとはどういうことなのだろう。「日本的アート」あるいは「非欧米的アート」はありうるか? ありうるとすれば、それはどのようなものなのか? アート界のView More >

メゾンは常に芸術で満たされていなければならない 優れた職人の手による高品質の製品づくりにこだわり、世界を代表する高級ブランドとして成長を続けてきたエルメス。総売上の約3分の1を占めるともいわれる日本を中心に、アジアにおけるアートへの取り組みを探ってみた。 取材・文:編集部 183View More >