
パヴェル・ブライラ「阿呆船」
愚者の船はどこに向かうのか……
文 / 杉田敦
リスボンの中心街に清貧の人、聖ドミニコの名前を冠した、サン・ドミンゴス広場がある。サクランボのリキュール、ジンジーニャを飲ませる立ち飲み屋があり、観光客や、アフリカの旧植民地の人々が集まる賑やかな場所だ。傍らには、同じ聖人の名前を戴く教会もある。幾度とない震災、火災を潜り抜けたその教会は、他の教会にはない独特の空気を漂わせている。広場の中央に、斜めに切断された球体状のオブジェがある。2008年に設置されたそれは、1506年の4月、リスボンで起こったユダヤ人の虐殺の記憶を呼び覚まそうとするものだ。周囲の壁には、自らを戒めるように34もの言語で「寛容の街、リスボン」と記されている。その時代、ポルトガルを襲った疫病、干魃による荒廃の責任を、特定の民族に擦りつけるように先導したのは、先の聖人が興したドミニコ会の修道士たちだった。数千にも達したとされる犠牲者を出した虐殺の25年後、リスボンを震災が襲い、13世紀に建立された教会は再建を余儀なくされている。篤信家たちから寄付を集めて建て直されたものの、地震学が生まれた契機とも言われる論文をイマヌエル・カントに書かせることになる、1755年のリスボン大震災によって、聖具室と礼拝堂を除いて再び灰燼に帰している。表向き、政治的な姿勢を強調することのないミュンスター彫刻プロジェクトの深層に、ホロコーストの気配が遺っていたのは決して特別なことだったわけではない。同様な徴は、そこここにある。
開催地の記憶に対して、国際展の来場者が陥りやすい態度について前稿で触れたが、当然それは自分自身についての指摘でもある。芸術表現が、その土地に本来なかったはずのものを出来させる場合が多いことを考えれば、それを目的に訪れた人々は、多かれ少なかれその土地の記憶に差し向けるはずのエネルギーの一部を、そちらに割り振らなくてはならなくなる。つまり、本来であれば抱くことができたはずの意識を、むしろ削がれることになるのだ。この逃れ難い罪深さを解消する方法は果たしてあるのだろうか。安易な贖罪に陥ることを回避しなくてはならないのは言うまでもないが、ひとたびそうした罪の意識に囚われてしまうと、なかなか逃れることが難しくなってしまう。カッセルに向かうホドスは、所用のため、少し遠回りをしてオランダのネイメーヘンの大学を経由することになったのだが、そこでもその地の記憶への意識は抑えることができなかった。いやひょっとすると、用件と同等かそれ以上に、むしろ特定の記憶への関心がそこに行くことを選択させたのかもしれない。
とある研究会の発表が行われた大学の敷地に隣接して、T4作戦と表裏をなすナチスの痕跡が遺されていた。レーベンスボルン、生命の泉と名づけられたその計画は、T4作戦が排除という影の部分に当たるのだとすれば、繁殖という陽のあたる部分を担当していた。アーリア人の特徴を色濃く示す女性と、総統への忠心を固く抱く、ナチ親衛隊やナチ党員とのあいだで計画的な生産を行い、生まれた子供たちを、親から引き離し、最高の環境で集団育成しようと考えたのだ。確かに、絶滅と繁殖という対比だけをみれば、どちらが陰に相当するかは明らかなのだが、必ずしも文字通りの性質を具えていたわけではなかったのかもしれない。残されている写真資料を見てみると、翳りのない光輝に包まれたレーベンスボルンの様子は、それが皮膚の下に隠し抱いているものを想像したとき、むしろ底知れぬ不気味な闇となって迫ってくる。老人ホームとして利用されていると聞いていたのだが、周囲を柵で囲まれたそこは、すでに別の利用者のために身支度をしているようだった。かつて、完璧な養育環境として羨望を集めたはずの建物も、いまでは心理的瑕疵物件になってしまったということだろう。もちろん、それらの施設で純粋培養された人々を待ち受けていた運命も過酷なものだった。ドイツに対して徹底して抗戦したノルウェーでは、戦後、レーベンスボルンの子供を産んだ女性たちは逮捕され、子供たちもまたいわれのない差別を受けた。そのため、多くの人が出自を偽らざるをえなかったという。表面化していない扱いまで含めれば、さまざまなことがあったはずだ。施設出身であることを隠さなければならなかったことは十分に理解できる。最近になってようやく、老境に差し掛かった出身者たちが、和やかに集っている光景を目にすることができるようになってきた。救われた気持ちになるのは確かだが、一人ひとりの経験には想像を絶するものがあったはずだ。
ネイメーヘンからの快適なはずの列車の旅は、ドイツ側の機関車の到着の遅れで2時間の遅延となった。ハノーファー駅に降りてみると激しい雨と風で、機関車の遅れはそのためだった。カッセル方面の列車は動いておらず、数分おきに出発ホームの変更がアナウンスされる混乱ぶりで、駅員に尋ねても乗客と同じアプリで確認するばかりだった。ホームからの階段は雨が流れ落ち、地下の連絡通路は踝ぐらいまで冠水していた。変更されたホームへ急ぐ旅行客が階段で足を取られ、そのはずみでスーツケースが落ちてくる……。前回のドクメンタのジャネット・カーディフとジョージ・ビュレス・ミラーの映像のなかで、中央駅に集められたユダヤ人たちが慌ただしくスーツケースを開け閉めする光景を思い出していた。本当に、彼らはどのような気持ちで駅に向かったのだろうか。ミュンヘン行きという言葉がかすかに聞こえたような気がした。目の前の駅員に確認して、別のホームに置いてあった荷物を取りに戻り、急いで飛び乗ることができた。おそらくカッセル行きを望んでいた多くの人が取り残されたはずだ。奇跡的に路は開けた。しかしもちろん、ユダヤ人たちに対してそうなることは決してなかったのだ。

リスボン、サン・ドミンゴス広場

ネイメーヘン、元レーベンスボルンの建物

カッセル大学、工学系キャンパス内の、ヨーゼフ・ボイスの「樫の木7,000本」
カッセルのドクメンタは、最初あまり気乗りしなかった。もちろんそこには、先ほど述べた罪深さに対する気後れのようなものも関係していたのだろう。反動というわけではないはずだが、むしろ、今回のドクメンタとは関係のないものには抵抗なく足が向いた。ホテルから中心部に向かう途中、カッセル大学の電気工学とコンピュータ・サイエンス専攻のキャンパスがあった。注意していなければ通り過ぎてしまいそうなのだが、キャンパスの樹木の大半は樫の木で、傍らには玄武岩が添えられている。ドクメンタ7から8まで続いた、ヨーゼフ・ボイスの「樫の木7,000本」プロジェクトだ。ドクメンタのメイン会場、フリデリチアヌム前にも、本人自らと、彼亡きあと息子の手で植えられた樫の木が仲良く並んでいる。ひょっとすると、その土地の記憶を踏みつけてしまうというのも、これと同じことなのかもしれない。そうつまり、フリデリチアヌム前のそれは気に留めることができるけれども、町のそこここにある樫の木と玄武岩に対しては、まるで存在していないかのような視線を送ってしまうのだ。
市庁舎の前では、また異なる想いに囚われることになった。正面に向かって右手に、ぽっかりと空いた空間がある。スチール・メッシュの床材の下には、12mもの深さで、モニュメントが地中に向かって伸びている。前回のドクメンタの際、キャロライン・クリストフ=バカルギエフは、アーティスト、ホルスト・ホーハイゼルとともに地下に潜ってその清掃を行っている。ホーハイゼルのモニュメントは、1986年のコンペを経て設置されている。つまり、クリストフ=バカルギエフのドクメンタの以前からそこにあったものなのだが、5年毎に更新される現代美術の現在を期待して訪れた人々は、その存在に気づくことなくそこを通り過ぎてしまう。クリストフ=バカルギエフはそれに光を当てようとしたのだ。もちろん、それでもそれは一過性のことでしかない。予想していたことではあるが、再びそこが、来場者たちの注目を集めるということはないようだ。ときおり、足元に目を向ける人がいるぐらいで、静かな時間が包み込んでいる。しかしそもそも、その場所には「アシュロットの泉」と呼ばれる別のモニュメントがあったのだ。ユダヤ人実業家、ジグムント・アシュロットが1908年に寄贈したことからそう呼ばれるようになったそれは、泉の中央に高さ12mの砂岩でできたネオ・ゴシック様式のピラミッドを抱えたものだった。アシュロットがカッセルに残した業績は決して小さくない。ヴィルヘルムスヘーエ駅から旧市街に向かうフォルダーラー・ヴェステンと呼ばれる一帯は、緑豊かな通りや、広場やモニュメントが整備されていて人気の居住区だが、基本的な整備計画を立てたのはアシュロットだった。ホテルから市庁舎まで、いままさに辿ってきた道がそうだったのだ。実業家のモニュメントは、ナチス政権下には「ユダヤ人の泉」と呼ばれていた。やがてそれは市民の手で破壊され、水受けの部分には花が植えられ、「アシュロットの墓」という蔑称で嘲弄されるようになる。忘れ去られていくホーハイゼルの記憶の背後に、さらに遠のいてく記憶が連なっているのだ。
ドイツの記憶について考える際、ホーハイゼルは重要な作家のひとりだと言えるだろう。建築家でもあるアーティスト、アンドレアス・ナイツとの協働も多く、前回触れた、T4作戦の記憶を呼び覚まそうとする灰色のバスの移動式モニュメントもそのひとつだ。カッセル中央駅には、ガラス・ケースで蓋われた台車が置かれている。台車に載せられているのは、カッセルの学校の協力を得て、1988年から行われたワークショップで制作したものを集めたものだ。かつてカッセルに住んでいたユダヤ人の名簿を持参したホーハイゼルは、そのなかのひとりを学生たちに選ばせ、どのような人だったのか、どのような死を迎えたのか、故人に関する調査を依頼した。調査結果は一枚の紙片に記され、それぞれの紙でひとつの石を包み、開いてしまわないように紐をかけた。包まれた石は学校ごとに小さなコンテナに分けられ、「考える石のアーカイヴ」と名づけられた。台車の上にあったのはこのアーカイヴだ。カッセル駅から絶望へ向かって旅立った人々のために紡がれたささやかな思考は、果たして同じ線路から、彼らとは逆の方向に旅立つための一助となれるのだろうか。いずれにしても、いち早くユダヤ人がいない状態、ユーデンフライ(judenfrei)を達成したと言われるカッセルの人々にとっては、行き先の定かでない台車は胸に突き刺さる記憶に違いない。前回のドクメンタでは、カーディフ=ミラーの「もうひとつの駅」が、iPodの映像で台車のところに向かうように誘導していた。おそらく、多くの人が足を運んだことだろう。残念ながら今回は、市庁舎前の地下モニュメントと同じように、顧みられるということはないようだ。もちろん、今回のドクメンタにも、かつての記憶を呼び覚まそうという試みがないわけではない。ロイス・ヴァインベルガーのインスタレーションは、明らかにカトリーヌ・ダヴィッドのドクメンタ10のときの参加作品、カッセル中央駅の線路を利用した「植物の彼方にあるものは植物と一体化している」を反芻しようとするものだ。ユダヤ人を乗せた列車が発着したとされる、現在は使われていない線路に植えられた緑。題名にもあるように、その場所の記憶とも一体化している線路の植物は、現在では常設展示として扱われている。オランジェリーの前のカールスアウエにある今回の作品は、20年前とほぼ同型の緑を剥がし、若干溝を穿つようにしたものだ。両者の関係は明らかだが、常設との対応を示すものはどこにも見当たらない。虚しく緑を剥がされたそこに、かつてユダヤ人たちを運んだはずの車両を想い浮かべることができた人はいるのだろうか。奇しくも、ヴァインベルガーの常設展示はホーハイゼルの台車の少し先にある。記憶と一体化した植物も、考える石のアーカイヴも、残念ながら振り返られることはなさそうだ。

ホルスト・ホーハイゼル「アシュッロトの噴水」

アブバカール・フォファーナの展示
記憶に触れようとする作品が増え続ける一方で、来場者たちは、自身の足元を忘却で洗われ始めていることに気がつくことができない。この困難のなかでどう振舞うことができるのだろうか。おそらくそうした想いが原因して、あまり集中することができないまま会場を巡ってしまったのだろう。小さいことだが、通常よりも厳しく、手荷物のサイズを検査されたのも気になった。アテネの寛容さのかけらもないじゃないか……。もちろん拗ねた気持ちばかりが原因だったわけではない。隅々まで管理された空間に入れられるような、言いようのない気持ち悪さが耐え難かったのだ。杓子定規なスタッフも気になった。指示されたことを言い訳にしたのはアイヒマンではなかったか。前回のドクメンタで、ドクメンタに関わる警備やスタッフのために、専門家によるマナー向上のための事前講習を行ったのはアナ・プルヴァチュキだった。今回こそそれが必要なのではないだろうか。アブバカール・フォファーナの展示で、アテネのアトリエ襲撃の事実が触れられていないことも気になった。ロジャー・バーナットの、モノリスのレプリカの盗難についても同様だ。どちらも、前々回ここで触れたものだが、個別の作品に対するものではあるものの、今回のドクメンタに対する意志表示ともとれるものに対して、応答するための時間は充分あったはずにもかかわらず、わかりやすいかたちで対応されていないことが釈然としなかった。自身の姿勢を明らかにしないまま行われるどのような提示に意味を見出せというのだろうか。
しかしもちろん、こうした事態は、芸術が社会や政治など、世界の問題に視線を送るようになったからこそのものであることは確認しておくべきなのかもしれない。ドイツの近代化のプロセスの空隙を埋めるために、あるいは退廃芸術によって傷つけた表現者の名誉を回復するためにという目的で、ドイツ園芸祭の一環としてドクメンタが開催された当時、おそらくこうした問題は、問題にならないというよりは、問題を構成することにさえ至らなかったはずだ。時間の流れは、想像を超えた大きな変質をもたらしたようだ。ハンス・ハーケのベタ焼きは、そんな時間の隔たりを静かに物語っていた。通常、メイン会場としてそのときのドクメンタを象徴するような展示が行われるはずのフリデリチアヌムは、今回、ギリシアの国立現代美術館(EMST)の収蔵品による展示が行われていた。わかりやすい交流とでも言えばよいのだろうか。そこに、ハーケの手で撮影された2回目のドクメンタの記録写真があった。引き伸ばされたものも何点かあったが、むしろ、ベタ焼きというフィルム写真ならではの表現が、イメージそのものだけでは捉え難い臨場感を捉えていた。ピントのボケた、けれども理想に燃える、アーノルド・ボーデの瞳。ノイエ・ギャラリーには、ボーデ自身の作品も展示されていた。またそれらに紛れ込むように、ゲルハルト・リヒターのボーデの肖像画も展示されている。リヒターというドクメンタの常連の手で描かれた歪んだ肖像は、まるでボーデの時代からの距離を物語っているようでさえある。しかし、たとえそうなのだとしても、現在の状況はボーデに起源を持つものに違いない。彼が始めたからこそ、ハラルド・ゼーマンがテーマを設定し、ヤン・フートがホワイト・キューブを抜け出し、ダヴィッドがレクチャーや討議という不定形なソフトウェアをインストールし、オクウィ・エンヴェゾーが世界の問題への覚醒を促したのだ。そしてだからこそ、現在のある意味ダブル・バインドとも言える状態での振る舞いが問題にもなるのだ。芸術が世界の問題に対して積極的な言及を試みるからこそ、自身がどのような姿勢でそうしているのかが問われるのであり、そしてまた、そうすることによって毀損してしまっているものがないか、注意が払われるようになったのだ。
おそらく、こうしたことが複雑に影響していたからなのだろう、具体的な言及に力点を置くものが心に響いてこなかった。略奪に近い方法でナチスに接収された芸術作品をテーマにしたマリア・アイヒホルンも例外ではなかった。そこには、アテネのプロジェクトよりも、明らかに多大なエネルギーが注ぎ込まれていた。しかし、その規模と徹底にもかかわらず、破綻の見当たらないプロジェクトは、不首尾な結果を示さざるをえなかったアテネよりも魅力ないもののように思えてならなかった。アテネで服毒死した哲学者のことが想起された。彼の思想を、不完全であるからこそ完全もまた手に入ると読み替えることはできないのだろうか。いずれにしても、アテネから学ぶことをスローガンに掲げる展示の一部として見せられることに違和感が残った。北対南という構図に原因する分断は避けなくてならないのだとしても、けれどもそのとき、近代的な思考の徹底こそが問題になっていたことを忘れてはならない。近代的な思考や方法への依拠は仕方のないことだとしても、そのとき、どのような自省を並置することができるかということが重要なのは言うまでもない。アイヒホルンのプロジェクトは、個展のようなかたちで出逢うことができればよかったのかもしれない。ナイーム・モハイエメンの場合も同様だった。アテネの映像は、フランコ・”ビフォ”・ベラルディの言う、金融資本という抽象に対する強力な対抗手段になりうるかもしれない、「言語における過剰」を体現している可能性を感じさせるものだった。父親の体験を下敷きとした不整合なアテネの映像と比較したとき、収まりのよすぎる体裁は、ある意味で啓蒙的で退屈でもあった。彼の『South』のテキストに照らしても、何かそぐわない方向のものを見せられたような印象が付き纏った。もちろん、アイヒホルンにしてもモハイエメンにしても、興味が持てない内容ということではないのだが、それを芸術が担うべきだという必然性に欠けているような印象が拭えないのに加えて、それをある意味で大文字の西欧的知性の枠組みで取り組もうとする姿勢が理解できなかった。分節化された知の体系に揺るぎない信頼を置くことができるのであれば、その意味を呼吸することもできたのかもしれない。けれども現在、知の瓦解とも言えるような状況にあることを考えれば、そしてその超克を、アテネに、南に学べという視点から試みようと謳うのであれば、ビフォのような姿勢に対する期待の方が勝ってしまう。少なくとも彼らの場合、アテネではそれを感じることができたのだ。あるいはそこに、詳細な事実の提示が、むしろそれを注視させることによって、足元にあるものを忘却させることになるのではないかという疑念も関係してくるのだろう。いずれにしてもそうした意識が、素直にそれらの作品と向き合うことを妨げていた。

ハンス・ハーケのドクメンタ2の記録写真のベタ焼き。中央にアーノルド・ボーデの姿が見える

ゲルハルト・リヒターによるアーノルド・ボーデの肖像
記憶を蔑ろにしているのではないかという罪の意識は、ますます深まるばかりだった。そのため逆に、元々そこにあるものへの意識ばかりが強まってしまう。ミュンスターにもあったギュンター・デムニヒの「躓きの石」もそのひとつだった。10cm角で上面に名前を刻印された真鍮を施したコンクリート製のブロックは、最初はなかなか目にとまらないが、一度慣れてしまうと、街中でも容易に見つけることができるようになる。ユーデンフライの街、カッセルには、「躓きの石」が数多くある。街中でそれを見つけることで、なぜか少し気持ちが落ち着くような気がした。そこから追い立てられたユダヤ人たちに関しては、ホーハイゼルの「考える石のアーカイヴ」のなかに何かしら記されているはずだ。カッセル中央駅では、移送のための列車が彼らを待ち受けていたはずだが、いまはただ、半ば見捨てられた線路跡にヴァインベルガーによって植えられた植物を通してその姿を想像するしかない。ホーハイゼルの灰色のバスのモニュメントもカッセルにやって来ていた。クリストフ=バカルギエフのドクメンタの閉幕後の11月から約一年間、フリードリッヒ公園のマリア・ミヌヒンのアクロポリスを挟んでフリデリチアヌムとは反対側の緑道に、静かに停車していたようだ。もちろん、すでにそれはそこを発っているのだが、想像してみることはそれほど難しいことではない。もともと、当時の市民たちにとっても幻のような存在だったのだ。見えているにもかかわらず、見えないものとみなされ、無視を決め込まれていた存在だったのだ。むしろ、実際の姿を目にするよりも、想像する方が相応しいのかもしれない。市庁舎前の噴水に名を残す人物に代表されるような有力者も含め、活況を呈していたというカッセルのユダヤ人コミュニティのメンバーは、老若男女を問わず、躓きの石のある家々から連れ出されていった。カッセルの中央駅に辿り着いた彼らは、カーディフ=ミラーの映像よろしく慌ただしくスーツケースを開け閉めして荷物を確認し、当時はまだカッセルにひとつしかなかった鉄道駅のプラットフォームから無慈悲にも送り出されていった。街中に滑るように乗り入れて来た窓を覆われた灰色のバスは、心身に問題を抱えていると決めつけられた人々を満載にして、家族たちも薄々そう気づいていたはずなのだが、死出のドライヴに旅立っていく。市庁舎の前のユダヤ人の墓には、善良そうな見かけの人々が花を手向け、総統への忠信に恍惚としたまま、満面の笑みを浮かべて家路に着いたのだ……。こうした光景は、ドクメンタが開かれることがなくても、常にそこに幻影のように漂っているはずのものばかりだ。幻影を、せめて幻影として確認することはできないのだろうか。展示による具体的な言及が進めば進むほど、複雑な想いが無視できなくなってくる。
芸術表現の社会や世界に言及しようとする姿勢は、ある意味で芸術の成熟を示すものでもあるだろう。すでに触れたように、その地の記憶と展示に関する問題は、ドクメンタ自体も大きく貢献してきた、こうした芸術の成熟によるところが大きい。またそのこと自体は、前向きに受け取るべきことでもある。しかし一方で、こうした状況に、どうしようもない危うさがあることについても看過することはできない。アーティストは、次から次へと社会の問題を渡り歩き、ある種啓蒙的なやり方で、その問題の所在を明らかにしていく。しかし一方でそうすることが、たとえ幻影のようなものに過ぎないのだとしても、ゲニウス・ロキ的な記憶の断片を忘却の彼方に追いやるのであれば、当然それは問題に違いない。来場者の場合も、確かに、アーティストの提示するものに触れることで、いたく心を動かされ、自身の活動が大きく影響されるということもあるだろう。その意味は計り知れないが、眼前の問題がまさに忘却や失念の底から浮上してきたように、いま経験している覚醒の時間が、一方で別の記憶をその同じ底に押しやっているのだとすれば、アーティストと同じ問題を抱えているということになる。もちろん、社会や政治の問題に関わろうとする表現の問題はこればかりではない。現実の問題は表現に対してある種の抑制として働くこともあり、また問題が切実であればあるほど、その処し方は定型のものになりがちになる。こうした表現自体のコモディティ化も見逃せない問題に違いないし、また、アーティストのどこか啓蒙的な姿勢が、彼らをひとりのアクターとして措定することには成功するものの、けれども他方、来場者に対しては同様な意識を抱くことを阻害することになりかねないということも危惧される。そもそも誰であれ、種々の問題がいたるところで提示される事態を前にすれば、呆然としたまま無力感にとらわれることになるはずだ。たとえそうならない場合でも、アートというかたちで提示された問題については考察したり、介入したりすることはできるけれども、眼前にある現実の光景からは何もアフォードされないというのであれば皮肉すぎる本末転倒でしかない。足元で進行しているかもしれない忘却という問題は、そうした笑えない事態の可能性を示すものでもある。
またもちろん、こうした事態は、戦時下の第三帝国に関する問題に限った話ではない。今回のドクメンタで、種々のメディアで取り上げられた活動がある。ノイエ・ノイエ・ギャラリーの一階で、「ハリットの友人たち(The Society of Friends of Halit)」という名義で、極右組織NSU(国家社会主義地下組織)の連続殺人事件を扱った展示が行われていた。トルコ系の住民を標的にしたその蛮行の9番目の犠牲者になったのは、カッセルでインターネット・カフェを営んでいたハリット・ヨズガットという21歳の青年だった。プロジェクトは、ロンドンの調査機関と協力するかたちで、その事件に関する調査、分析を行い、それまでの警察を中心とした事実認定とは異なる結論を導き出していた。「77㎡ 9.26分」と、インターネット・カフェの面積と、事件に関連する時間をタイトルにしたヴィデオは、ドイツの諜報機関の職員が極右組織にまで秘密裏に送り込まれ、しかもその証言に偽証の疑いがあることを明らかにしていた。もはや芸術という枠組みさえ関係のない、圧倒的な検証に基づく新たな事実の提示は、経緯を辿るためには相当な集中力を要するものだったが、多くの人が集まり、関心の高さをうかがわせていた。もちろんそこでの調査結果や、芸術表現の枠自体を拡張しようとする、あるいはその不自由を取り除こうとする姿勢が問題なのではない。2006年に起こった事件が、未だに法廷での解決をみておらず、しかもそこに、国家機関が関わっているという事実は、この展示によってしか知ることができなかったものだ。だが同時に、複雑な思いにもさせられることになる。というのも、今回のドクメンタの最北部、ノルトシュタット公園にアグネス・デネスの緑のピラミッドを観ようと訪れた来場者たちは、最寄りのトラムの駅にハリットの名前が冠せられていることに気づくことはおそらくないはずだ。あるいはその駅を挟んでピラミッドと反対側の通り沿いの広場の、ハリットを含めた犠牲者たちの慰霊碑についてはどうだろうか。おそらくほとんどの人は、ノイエ・ノイエ・ギャラリーで感銘を受けたのだとしても、慰霊碑に目をくれることもなく、トラムの駅名に気づくこともなく、さらにはその通りを暫く行ったところに現場となったインターネット・カフェがあったことも知らないまま、次の目的地に向かって足早に立ち去って行くことになるはずだ。この構造が持つ危うさ、危険さは一体何なのだろうか。言うまでもないことだが、自身の慧眼を示したいわけなどではない。自分自身も、調査機関が明かしたとされる証拠に興味があったからこそ事件を知ったのだし、ミュンスター以来、捻くれた態度で足元ばかりに注意を配っていたからこそ、幸いにもそれらの名称やオブジェに気づいただけのことに過ぎない。同様な無視や不注意を、間違いなく、さまざまな場所で数限りなく行ってきたはずなのだ。注意を向けつつ、けれどもそれゆえに、注意を削がれてしまうという事態。この問題への対処の難しさこそが、カッセルから受けた最大の印象なのかもしれない。

カッセル中央駅、コンコース

トラム、ハリット広場駅

パヴェル・ブライラ「阿呆船」
15年前のオクウィのドクメンタで、印象に残っている作品がある。「ヨーロッパのための靴」と題されたそれは、寒そうな操車場で行われる作業を淡々と記録したものだった。カッセル中央駅、駅舎の会場で最初に見た作品だが、その会場から回り始めたので、オクウィのドクメンタで最初に目にした作品ということになる。作者はパヴェル・ブライラ、モルドヴァ出身のアーティストだ。かつてモルダヴィア公国だった東欧の一帯は、現在、西側はルーマニアに、東側は旧ソヴィエト連邦のモルドヴァ共和国に分かれている。旧ソヴィエトの軌間を走る列車は、ルーマニア以西のヨーロッパに向かうために、ヨーロッパの軌間を走行できるように3時間かけて台車を交換しなくてはならない。ヨーロッパに入るために、靴を履き替えなくてはならないというわけだ。ブライラの映像は、淡々とその様子を16mmで撮影したものだ。あまりにも何も起こらない映像と、その裏側に貼りついている問題とのコントラストが、強く印象に残ったのを記憶している。そのブライラが、シムジックのドクメンタにも参加していた。アテネでは、カスパー・ケーニヒがディレクションしたサンクトペテルベルグのマニフェスタのための作品が出展されていた。温暖なソチで開催されることになった冬季オリンピックのために生み出された人工雪。冷凍保存された人工雪は、人間たちのちぐはぐな愚行の結晶でもある。阿呆船をモチーフにしたカッセルの作品は、実際に運行している路線バスを利用したもので、乗車することもできるようになっている。バスの窓には、エーゲ海を思わせる鮮やかなブルーの水が封入されていて、停車や発進の度に大きく揺れ動いた。カッセルの街を透かし見せるエーゲ海の揺れは、当然のことながら、頼りなげなボートに命を託した難民たちが見つめたであろう海原を連想させる。彼らが身につけていた救命胴衣は、アイ・ウェイウェイの手で横浜に運ばれたらしい。アイ・ウェイウェイは、難民危機というものは存在しないとツィートしている。存在するのは、難民のではなく、人類の危機だという文言がそれに続く。そうした事態を救えない、許していること自体が、人類の危機だというのだ。ブライラの阿呆船に揺られながら、難民を想起するのは間違っているということだろう。紛れもなく、難破しそうな阿呆船で、希望のない暗闇に向かっているのは人類そのものなのだ。
ブライラの船に揺られながら、自然と思い出していた光景がある。マンティア・ディアワラの映像作品「An Opera of the World」のなかの、レスボス島に向かう難民のボートが海原を進むシーンがそれだ。ディアワラについてはすでにこの連載で触れたが、アテネでは上映時間が限られていたため見ることがかなわなかった。カッセルのバリ・キノでは連日上映されていた。どう考えても、レスボス島のあるギリシアでこそ、もう少し上映の機会を設けるべきだったはずだ。けれどももちろん、ブライラの作品と呼応することができたという意味では、カッセルならではの良さというものもあるのかもしれない。映像には、繰り返し、エーゲ海を漂う難民たちのボートが映し出されていた。一方それとは別に、作者の母国マリで上演された、チャドの詩人クルジー・ラムコの『ヴィント・ウエア』を台本とするオペラのシーンが進行していく。こうした対位法的な構成は、どこか友人でもあったというエドゥアール・グリッサンの思想を想い起こさせる。ニジェール河畔の特設ステージで上演されたというオペラは、サヘルと呼ばれるサハラ砂漠に隣接する半乾燥地帯を舞台に、悲惨な状況に生きる人々の姿を描いたものだ。人々は北へ、つまりヨーロッパへと、密輸業者たちによって誘惑される。一方、物語自体は、オペラという北を代表する表現形式を、南に逆輸入するかたちで紡がれていく。サヘルの物語自体も、単にサヘルという地域のものに終始してしまうわけではない。差し挟まれるレスボス島のシーンがもたらす対位法的な効果によって、物語は混沌とした世界、グリッサンの言うところの全-世界に波及していくような余韻を漂わせることになる。
時系列に忠実にという本稿の心がけからは大きく逸脱するが、ドクメンタの出展作品のプロデュースを担当したリスボンの独立系美術学校maumausのディレクター、ヨルゲン・ボックの企画で、5月から9月までという、ほとんどドクメンタと重なる会期なのだが、リスボンの市立ギャラリーで彼の映像作品がまとめて展示されていた。ディアワラはグリッサンから大きな影響を受けている。グリッサンへのインタヴューを基軸とした「関係性のなかのひとつの世界」という映像はそれを象徴するものだろうし、リスボンの展示の最終日に行われたレクチャーでも、それを隠そうとしなかった。グリッサンは、アンティル諸島という数千とも言われる島々に、もちろん共通する部分はあるとしても、言語や風習、歴史や背景など、それぞれに相違を持つはずの人々に、けれどもある種のアイデンティティが成立することを示してみせた。また、エメ・セゼールに師事したこともあり、ディアスポラの問題についての考察を深め、そうした境遇だからこそ全-世界という提案も可能になるという、アクロバティックな転倒によるポジティヴな視点の可能性を提起した。いずれにしても彼の思想は、いわゆる近代の外であることを望むものであり、事実、ある意味で外部からのよく通る、澄んだ声なのだ。大陸的思考に対し、群島的思考という、曖昧さの思考の可能性をみようとしたのは、そうした姿勢を象徴するものだと言えるだろう。
グリッサンの思想は、ここでもたびたび触れてきた、言語の過剰としての詩に期待を寄せるビフォにも重なるところがある。グリッサンは群島的思考の側から、ビフォは大陸的思考の側からそこに接近したという違いはあるとしても、両者の間に大きな隔たりはない。グリッサンもビフォも、共にジル・ドゥルーズに依拠していることを考えてみるのもわかりやすいかもしれない。ソーカル=ブリクモンのサイエンス・ウォーズ事件以降、ドゥルージアンと称していた人たちが霧散してしまった日本とは異なり、彼らの場合は、本質的な重要さをそれまで以上に深く呼吸しようとしている。またグリッサンの思想は、むしろ、ニコラ・ブリオー以上に、関係性の美学の本質を示していることにも注意しておきたい。合目的な相互作用などなく、けれども共にいることだけでも、もたらされるものがあるかもしれない。明らかにそれは、ディアスポラによってこそ可能になる全-世界という転倒や、曖昧さや過剰こそがシステマティックな大陸的思考に対抗しうることになるという考えの延長上にあるものだろう。

リスボンの展示会場のマンティア・ディアワラ
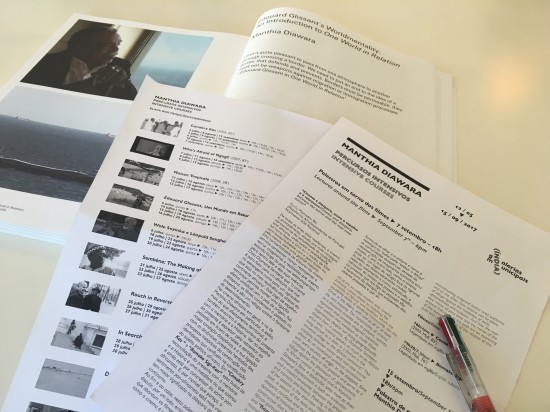
リスボンのディアワラ展のペーパーと、『South』 第6号のディアワラのテキスト
ディアワラの映像を思い浮かべながら、グリッサンの自由を想い、ブライラの車窓で波打つエーゲ海の青を見つめながら、アイ・ウェイウェイの言葉を反芻する。世界こそが破綻して、誰もがひとりの難民なのだという意識がむしろ心地よさを増してくる。一年の短期滞在とはいえ、ヴィザの取得や延長のために、移民局や役所とのやりとりに辟易としてきた、ここ数ヶ月間の個人的な体験も関係しているのかもしれない。あるいはそもそも、アイ・ウェイウェイの言葉も、それと呼応するかのようなブライラの船での体験も、何よりも当事者であることを強く求めているということだろうか。確かに、分節化された事象の提示は、どこかそれに対する客観的な観測者という立場を刻印してしまう。ロジャー・ビュルゲルとルート・ノアックのドクメンタ12が、その前後のドクメンタと比較して魅力を欠いていたのはそれが原因だったのかもしれない。グリッサンの言い方を借りれば、大陸的思考が、その破綻にもかかわらず自省を内在しないとき、説得力を持たないのは当然のことでもある。もちろん、大陸的思考の破綻とそれに対する自省の意識は、そう簡単に手にすることができるものでもない。例えば、カルチュラル・スタディーズがひとりのアクターとしての姿勢を思想家に求めようとしたとき、抵抗や躊躇があったのは無理のないことでもある。いずれにしてもビュルゲル=ノアックのドクメンタは、近代の、グリッサン的にいえば大陸的な枠組みにとどまるものでしかなかった。シムジックのドクメンタには、表面的にはどこかビュルゲル=ノアックに似ているという印象があるが、両者に決定的に距離があるのは、シムジックがある意味でパフォーマティヴな姿勢を重視していることだろう。確かに、冒頭で触れたように、さまざまな意志表示に対する応答の欠如に対しては不満が残るものの、それでも種々の討議に積極的に関わり、アテネに居を移し、参加困難なプレ・イヴェントを数多くこなし、メアリー・ジグーリのパフォーマンスに所在無げに紛れている様子は、客観的な観測者であろうとする大陸的思考の限界を理解しているからのものに違いない。ディレクターもまた当事者のひとりとして姿を現すという姿勢は、クリストフ=バカルギエフが巧みに取り組み成功していたものだ。充分だとは言えないが、シムジックもそれを行おうと努めてきたのだろう。また参加したアーティストも、それぞれの角度からそれを促してもいた。ブライラのボートの揺れが覚醒することを求めたのは、来場者である自分たちもまた当事者のひとりだという意識だろう。ノイエ・ノイエ・ギャラリーの一階の二箇所に設置された、マリア・ハッサビのスポット・ライトは、強烈にそのことに対する自覚を促すものだった。圧倒的な光の充溢のなかで、逃げ場なく捕らえられた来場者たちは、彼ら自身が当事者であるということをするどく突きつけられることになる。あなたなのだ、あなた以外、そこに誰もいないのだ……。また同じ会場の三階には、同じくハッサビの手で、ピンク色のカーペットが敷き詰められていた。そこは、ハッサビがパフォーマンスを行った余韻の残る場所などでは決してない。そこは、今まさにそこを通り抜ける人々によって、つまりそう、あなたによって、演じられ、踊られる、そのためのステージなのだ。
わたしたちは当事者なのだ。それは、国際展に足を運び、訳知り顔で展示に頷きながら、足元の記憶を踏みにじる人物なのだ。難民の問題に心を痛めながら、それが難民の危機だというように認識できても、人類の危機だというようには認識できないかもしれない人間なのだ。しかし、例えそうなのだとしても、当事者として、何かの振る舞いを行うことができる場所に立ってもいるのだ。シムジックのドクメンタが、もしそのことを伝えるためのものなのだとしたら、数多の評判ほど悪くはないのかもしれない。すべてを把握してもらいたくないかのような膨大な出展者数も、明らかにクリストフ=バカルギエフのカーディフ=ミュラーの展示の二番煎じにしか見えないようなカールスアウエの音響作品も、馬脚を露わにしているかのような大陸的思考への諂いも、もはや問題ではないのかもしれない。リサーチのために膨大な時間が費やされつつも、けれども問題は個々の事実にあるのではなく、来場者それぞれが当事者であるという確信を手にすることだというのであれば、もはやそのアウトプットはどのようなものでもかまわないだろう。

マリア・ハッサビの「Staging」、ライティング・ウォール#1
ちょうどそう思い始めていたときのことだった。アート関係のメディアで偶然目にした、ギリシアの小島、イドラ島のオープニングの光景が、すべてを台無しにしてしまった。ピレウスから高速艇で1時間ほどのそこに、元屠殺場を利用した展示スペースがあり、カラ・ウォーカーの個展のオープニングが行われたのだ。リゾートのような場所で開かれた享楽的なパーティーに、名だたるアーティストやキュレーター、評論家などが集結したらしい。高速艇で向かったものもいれば、プライヴェート・ヨットで訪れたものもいるという。ウォーカーの個展のオープニングではあるものの、アテネの会期も終盤に差し掛かりつつあった6月中旬ということもあり、国際展の集中した今年のある種の中締めとして開催された趣があるとも記されていた。展示スペースを運営しているのはDESTE財団、キプロスのニコシア生まれの実業家、ダキス・ジョアヌーが立ち上げた現代美術のための財団だ。ジョアヌーは、マウリツィオ・カテラン、マシュー・バーニー、ジェフ・クーンズなど、錚々たるアーティストのコレクターとして知られるだけでなく、財団の活動としても、1999年から、ギリシアの若手アーティストの奨励を目的としたDESTE賞を設けるとともに、アテネ北部、ネオ・イオニアに現代美術の展示スペースを構えるなど積極的な取り組みを行っている。一見したところ活動そのものに問題はなさそうなのだが、しかし、同じエーゲ海の東端では、トルコからわずか15kmほどの海を渡るのに命をかけている人々がいる。あるいは、そのために費やされるなけなしのお金のことを想うとき、蕩尽としか思えないような豪華な集いの光景は、そしてそれに能天気に浮かれてみせるメディアは、醜悪なものにしか思えなかった。何という無神経、何という思い上がり。しかも、仕方のないことなのかもしれないが、そこにシムジックの姿を認めたとき、釈然としないを通り越して悲しい気持ちが込み上げてきた。ドクメンタに期待して、なんとか都合をつけてアテネまで訪れた人も数多いはずだ。彼らはそこで、問題を共有し、世界の姿を思い浮かべ、まったく異なる枠組みの可能性に思いを巡らせてみたはずだ。しかしすべては、同じシステムのなかのちょっとだけ目先を変えたトピックだったということだろうか。パーティーではドクメンタのことはどのように語られたのだろうか。シャンパンを片手に、肩をすくめて、深刻なことはもうたくさんだとでも笑い合ったのだろうか。同じ海を少し東に進んだところでは、救命胴衣に命を託した難民たちが、唇を震わせながらボートの上で縮こまっていたのだ。どのような神経がそうした振る舞いを可能にするのだろうか。確かに、一方で政治や社会の問題に言及するようなものが注目を集めるのだとしても、依然としてアートの世界を支えているのはアートのマーケットでもあるだろう。その双方に関わらざるをえないのは仕方のないことなのかもしれない。しかしだとしても、メッザードラやビフォが指摘するように、金融資本の専制という事態こそが問題なのだとすれば、確かにひとりのギリシアの実業家がその任を担うわけではないのだとしても、その一端に関わっているかもしれないものの掌の上で、陶然とするディレクターの姿は哀れでしかない。アイ・ウェイウェイが言うように、難民の危機など存在しないのであり、人類の危機が存在するのだろう。だがそれ以前にここには、非常にレヴェルの低い、稚拙なアートの危機がある。北対南という分断を避け、南という想像的な試みの場を積極的に考えようというとき、ディレクター自身が金融資本の酒宴で興じている姿は目にしたくない。あるいは、難民の問題をそれぞれのやり方で扱う作品を多く見せられながら、彼らが苦闘する同じ海で、無神経な嬌態を示しているのだとすれば、アーティストに責任はないものの、表現されたものすべての信頼度が失われてしまう。アテネもカッセルも、言ってみればレスボス島のためのものだったはずだ。決してそれは、水を語源とする島で開かれた、低俗な集まりのためのものではなかったはずだ。フレリデリチアヌムで国立現代美術館(EMST)のコレクション展が行われていたことについてはすでに触れたが、そのなかに、ジャニーヌ・アントーニの「睡眠」があった。レム睡眠時の眼球運動を記録し、翌日その記録されたパターンを織り、出来上がった毛布で眠りに着く。女性たちが置かれている終わりのない再生産の循環を、見事に表現した作品だ。実際に目にすることができたのは嬉しいことだったが、ジョアヌー・コレクションからEMSTに寄贈されたものだということは影を落とさないわけにはいかなかった。そのことで彼女の作品の意味が減じられることはないのだとしても、それでもそれは、後味の悪いものにしかならなかった。
会期終了前後、クリストフ=バカルギエフの1.5倍にも膨れ上がったドクメンタの運営予算のため、ドクメンタ株式会社が破綻の危機に瀕していることが伝えられた。もともと行政と収益、助成などのバランスを取る受け皿として採られた会社という形態であるから、破産の危機は乗り越えられたようだ。分散開催が原因だったとも言われたが、調査機関の発表によればアテネでの運営費は全体の1割程度に過ぎなかった。もっとも、開催地間の作品輸送コストの膨張は主な原因のひとつでもあったようだから、あながち分散開催に原因を求めることも間違ってはいない。しかし、いずれにせよシムジックが、こうした財政破綻こそを意図していたのだとしたら、それはある意味で見事だと言えるだろう。シリザのギリシアと同じように、緊縮財政ではない道を選択したというわけだ。しかし、おそらくそんな豪気なことではないはずだ。ブライラの阿呆船のように、愚かものたちを満載にして漂流する巨大な国際展が、難破して、救いの手を求めただけのことだろう。シムジックが費やしたであろうリサーチのための時間やエネルギーには頭が下がるが、子供のような結末は、むしろそのことによってアート全体の社会的未成熟を露呈することにしかなっていない。ブライラの船に揺られているのは、紛れもなくアートそのものだということだろう。

マリア・ハッサビの「Staging」、ピンクの床
ナノソート2017
no.1「シンタグマ広場に向かう前に……」
no.2「アテネ、喪失と抵抗の……」
no.3「ミュンスター、ライオンの咆哮の記憶……」
no.4「愚者の船はどこに向かうのか……」
no.5「幸せの国のトリエンナーレ」
no.6「拒絶、寛容、必ずしもそればかりでなく」
no.7「不機嫌なバー、あるいは、政治的なものに抗するための政治」
no.8「南、それは世界でもある」
杉田敦|Atsushi Sugita
美術批評、女子美術大学芸術文化専攻教授。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)など。オルタナティヴ・スペース art & river bank を運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ)、『Picnic』(増本泰斗との協働)など、プロジェクトも多く手がける。4月から1年間、リスボン大学美術学部の招きでリスボンに滞在。ポルトガル関連の著書に、『白い街へ』『アソーレス、孤独の群島』『静穏の書』(以上、彩流社)がある。
