 ピエール・ユイグ「After Alife Ahead」
ピエール・ユイグ「After Alife Ahead」
ミュンスター、ライオンの咆哮の記憶……
文 / 杉田敦
ドクメンタに限るのであれば、アテネを訪ねた足で、そのままカッセルに向かうというのが一般的だろう。アテネとカッセルの間には、5月末から6月末までのほぼ1ヶ月間だけ、週に2便、ドクメンタ14の公式航空会社、エーゲ航空の直行便が飛んでいる。それを利用すれば、移動はきわめてスムーズにいくはずだ。ナイーム・モハイエメンの映像作品のなかで、彼の父親をモチーフにした男が物想いに耽っていたのは、打ち棄てられたオリンピック航空の機体の翼の上だった。EUの介入で難航したものの、その元国営航空を買収したのがエーゲ航空だ。ギリシアの航空会社による運行ではあるものの、ドイツ企業によるギリシアの空港の運営権の買収を考えると、神経を逆撫するような企画に思えてしまう。カッセルに向かうことを躊躇したのは、それも理由のひとつだった。また、開催地が異なるとはいえ、同じ名称を戴く展示に集中するのは、ドクメンタだけを際立ったものにしてしまうようで、そこに向かう気持ちを萎えさせた。カッセルはどこかのタイミングで訪れることにして、少なくともそれまでに別の場所に足を運んでおきたい。ちょうど同じ時期、ミュンスターで彫刻プロジェクトが開幕する。オクウィ・エンヴェゾーのドクメンタ以降、アートが社会や政治の問題に介入していく傾向が強まるなか、ミュンスターには少し異質な超然とした印象があるのが気になっていた。超然と言えば聞こえはいいが、単に保守的な姿勢なのかもしれない。だがミュンスターにも、ハンス・ハーケのような政治的な表現を旨とする作家が参加している。にもかかわらず、総体として深刻な印象に覆われていないのはなぜなのか。今後ますます強まることが予想される芸術の政治化、社会化の在り方を考える上で、ミュンスターには重要なものがあるのかもしれない。いずれにしても、今回のドクメンタを相対化するためには、あるいはその背景やそれに対してアートがどのような姿勢をとるのかを考えるためには、適した選択のひとつだろう。アテネからのホドスを、拠点であるリスボンを挟んでミュンスターに向かうものにしたのはそうした想いだった。
 ミュンスター
ミュンスター
ミュンスターを訪れた回数を語ることは複雑な想いにさせられる。あらためてアートに関わってきた年月を思い知らされるからだ。初めて訪れたのは1997年、第3回目だった。駅に降りてすぐ、曽根裕の「バースデイ・パーティ」の映像が目に入った。名称に謳われている、彫刻の概念が冒頭から頼りなく崩れ去っていく。人工湖、アー湖の畔では、夏草の上に横たわり、水面を渡る風に吹かれながらイリヤ・カバコフの作品を見上げた。通り過ぎてしまいそうな小さな橋を探し出し、ようやく辿り着いたフィッシュリ&ヴァイスの菜園の東屋では、どこを観るべきなのかわからず呆然としたまま、けれどもどこか爽やかな気持ちに包まれていた。厚い木板と有刺鉄線で囲まれたハーケのメリー・ゴー・ラウンドも印象深かった。疲れ果てて呼び止めたタクシーの運転手が、市民に一番人気がある作品なんだと自慢気に教えてくれた……。ヴェネツィア・ビエンナーレやドクメンタと比較すればかなり小規模だが、同様のエッセンスは充分あり、作品が少ない分、ゆっくりと向き合うことができる。いま触れた作品には、いずれも大きな影響を受けたが、それはそうした時間の余裕がもたらしてくれたのかもしれない。またしばらくして、ミュンスターの彫刻プロジェクトを下敷きとして、もちろん独自の要素も加えながら、越後妻有アートトリエンナーレが開催されたことも忘れられない。日本の各地に類似したプロジェクトを散種することになるイヴェントが初めて姿を現そうとしたとき、そのアーキタイプでもあるミュンスターを経験していたことは、本人が自覚している以上に意味があったような気がする。従来にない形態のアート・プロジェクトが、なかば陶然と、無批判に受け入れられていくとき、多少なりとも距離を置いて考えることができたのは間違いなくそのためだ。ミュンスターは、さまざまな考えや疑問、確信を与えてくれたのだ。
そんなミュンスターに着いて最初に驚いたのは、どこか以前と異なる街の雰囲気だった。もちろん、10年ごとに数日、しかもわずか数回のことであるから、裏付けることができる類のものではない。これまでその街には、落ち着いた雰囲気の、よく整えられた、品のよい学術都市という印象を抱いていた。旧市街と反対側の駅裏にセックス・ショップなどが集まる一角があり、多少夜の街の気配が漂うものの、大都市のそれと比べればほとんどないに等しい。あくまでもそこは、人口の1/6程度を大学生が占める、教育と文化のためのドイツ北西部の中堅都市なのだ。そのような印象に囚われていたため、旧市街に入る前に駅裏の酒場に寄っておくことにした。事前の精進落ちというわけだ。カウンター横の床にうずくまる老犬の匂いがたちこめる店内で、店主と常連がダイスに興じている。店内のゲーム目当ての若者と、店主が何やら揉め始める。ゲームをしたいなら何か頼めよ。一瞬、険悪な雰囲気になったが気にするほどではない。居心地は悪くなかった。驚いたのはそこを出てからだった。第二次世界大戦で壊滅的な被害を受け、戦後、忠実に復興された美しい旧市街に向かうにつれ、物乞いをする人を数多く見かけたのだ。時刻は、すでに人通りが落ち着き始める頃になっている。ほとんどは白人で、老若男女、入り混じっている。最初に断ったように、あくまでも、きわめて乏しい経験に基づく比較に過ぎない。これまでミュンスターでは、むしろ逆の、つまりそのような光景とは無縁の、中産階級の人々が落ち着いた生活を営んでいるという印象を抱くのが常だった。それだけに驚きが大きかったのかもしれない。曖昧な過去の印象が崩れそうになる。10年ごとの印象よりも信頼できそうな比較対象もある。数週間前に訪れたアテネだ。実際に危険な目に合うことはなかったが、あまり治安がよくないといわれるオモニア広場の近くに宿を取ったこともあり、薬物常習者や街娼を目にする機会も少なくなかった。もちろん、物乞いをする人も見かけないわけではなかったが、しかしそれはごく少数だった。ミュンスターの、綺麗に整備された街並みとのコントラストが、余計にその印象を深めたのだろうか。
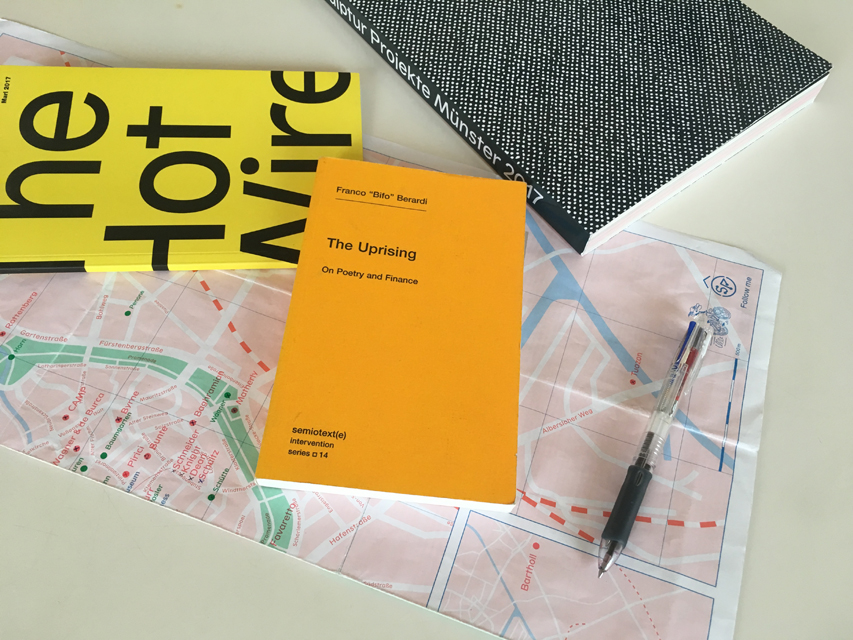 フランコ・”ビフォ”・ベラルディ、『蜂起』
フランコ・”ビフォ”・ベラルディ、『蜂起』
しかしこの不確かな印象は、無意識に抱いてしまっていた想いに注意を向けさせてくれた。ここでも繰り返し触れてきたが、国際展の集中する今年の背景には、ヨーロッパ南部の財政危機の問題がある。アダム・シムジックはそれを見つめようとしてきた。サンドロ・メッザードラやフランコ・”ビフォ”・ベラルディらは、そこにグローバル金融資本の専制という問題が隠れていると指摘し、その上で、いわゆる南がその問題を固有に抱えているわけではなく、世界が、巧妙で不可視な問題に呑み込まれているとも付け加えた。特定の場所という意味でのいわゆる南は、それが露呈した場所に過ぎないのだ。南とは特定の場所を指すものではないと指摘したのは、ニコス・パパスデルギアディスだった。彼によれば南は、そうした問題と向き合い、乗り越えるための空間なのだ。しかし、そのような理解を確認した上でも、どうしても意識は北対南というわかりやすい構図を見出そうとしてしまう。あるいはそれを、ヨーロッパ固有の問題だというように決めつけて、共有できない問題提起だと批判してしまう。いずれの場合も、問題を指摘することこそがむしろ分断を生むことになる。これまでここでは、そうした事態を回避することの重要性を強調してきた。しかしそれでも、無意識にどこかで、アテネという南に対応するステレオ・タイプな北を、わかりやすい敵対者の姿を、ミュンスターのなかに探そうとしていたのだ。いま触れた不確かな、曖昧な、実証しようのない印象は、そのような期待を抱いてしまっていたからこそのものだ。ミュンスターに対極のものを認めることを期待していた視線は、そうではないものを、むしろそれとは反対のものを、おそらく捉えてしまったのだ。
アテネでは確かに、ある種の抵抗や抗議が、ギリシアを追い詰め、搾取もしたであろうドイツという姿を浮き彫りにしようとしていた。新たなナチズムというような過激な表現さえ珍しくなかった。しかしそのドイツで、ミュンスターで、意外にも出合うことになった光景は、敵対するもののなかにも同じような抑圧や脅迫、搾取がある可能性を示すものだった。本当に敵対すべきものは何なのか。幻想に過ぎない敵対構造のなかに微睡んでいる限り、決してその真の相手、メッザードラやビフォが注意を促すものの姿は見えてこない。ステレオタイプな北と南の双方に、犠牲者たちはいまもなお積層され続けている。しかもその犠牲者たちが、表層的な敵対関係のなかで足掻きながら、分断され、敵対し続けている。双方が共通する問題に直面しているにもかかわらず、そのような過誤に陥っている限り、問題の核心が見えてくるということはないだろう。こうした専制の強化にしか結果しない悪循環に、どのように対峙すればよいのだろうか。少なくともミュンスターの街の光景は、再び、いたずらな分断に陥ることがないように警告していた。
 聖ランベルティ教会
聖ランベルティ教会
ハーケのような政治的な作品がありつつも、そうしたものに特化しているという印象もなく、あくまでもアートの、しかも変容しているとはいえ彫刻を謳うという保守的でもある姿勢は、国際展のなかでは異例なものだ。加えて、綺麗に整備された街並みや、学術都市というイメージは、社会や政治に直接コミットすることのない、現実と距離を置こうとする企画だという印象を強めることになる。しかし、ミュンスターにはかつてライオンがいた。彫刻プロジェクトのスタンプラリーに勤しむ視線には捉えられないかもしれないが、ミュンスターの旧市街に聖ランベルティ教会というカソリックの教会が聳え立っている。1941年8月3日、そこでライオンが吠えたのだ。クレメンス・アウグスト、フォン・ガーレン司教が吠え、噛み付いたのは凶暴な鷲だった。現在でも、ドイツの国章にあしらわれている鷲だが、フォン・ガーレン司教が吠えたとき、その鷲は両足の鋭い爪でしっかりと鉤十字を掴んでいた。彼が厳しく告発し糾弾したのは、優生思想に基づくT4作戦と呼ばれるナチスの政策だった。心身の障碍者や根治不能な病人、同性愛者などの抹殺計画だ。優生思想そのものは、チャールズ・ダーウィンの従弟、フランシス・ゴルトンによる自然選択の人為選択への読み替え以降、ヨーロッパではナチス以前から馴染みのあるものだった。1921年には、ヨーロッパで初めてデンマークで断種法が制定されている。非人道的であることは言うまでもないが、しかしそれでも、強制断種、結婚や産児の制限という段階でとどまっていた。しかしナチスは、その先へと踏み込んでしまう。ベルリンのティアガルテン4番地に本部があったことからそう呼ばれるようになった作戦の異様さは、フランツ・ルツィウスの史実に基づく小説、『灰色のバスがやってきた』などで一端を知ることができる。各地の病院を回り、処理対象者を集めたとされる目隠しされた不気味な灰色のバス。最大の処理が行われたとされるハルトハイム城から定期的に立ち上る煙、仄かに鼻を突く異臭。そして、何が起こっているか薄々気づきながら、誰もが口を噤まざるをえないような空気……。クリストフ=バカルギエフのドクメンタに参加者として名を連ねていたホルスト・ホーハイゼルの作品に、コンクリート製の灰色のバスの移動式モニュメントがある。2006年からドイツ各地を十数箇所巡っているそのモニュメントは、T4作戦当時の記憶を呼び覚まそうとするものだ。しかしもちろん、それでさえ、当時の異様な空気を再現することはできないはずだ。
T4作戦は、ホロコーストの予行演習としての意味があったと言われている。2015年のイスタンブール・ビエンナーレで、ピエール・ユイグは、マルマラ海に浮かぶ無人島、シヴリ島の沖合の海底に作品を設置した。おそらくその周囲には、1911年、オスマン帝国の近代化政策の一環としてその島に集められ、放置され、虐殺された、8万頭ともいわれるイスタンブールの野犬のうち、海を渡ろうと試みたものたちの骨辺が散在していたはずだ。役立たず、不幸の島とも呼ばれたそこでの蛮行は、4年後、アルメニア人に対する砂漠地帯への強制移住というかたちで再現される。100万人ともいわれるジェノサイドと、シヴリ島の事件との因果関係は、T4作戦とホロコースト同様、決して明確なわけではない。そもそも、予行とか本番という分類には意味がないだろう。シヴリ島やT4作戦には、予行としての意味を見るよりも、見つめなくてはならない問題が隠れている。シヴリ島の表向きの目的は、イスタンブールをヨーロッパの代表的な都市、パリやベルリンに匹敵するものにするための衛生的、外観上の処置であり、T4作戦のそれは、生産に寄与することができない人間への社会としての対応であった。字面だけを見る限り、どちらも近代化の過程にとって必要なものであるかのような上辺をしている。首肯できないのは言うまでもないが、確認しておきたいのは、ヨーロッパにおける優生思想の広がりにも、シヴリ島の虐殺そしてT4作戦にも、近代がある種の理由らしきものを提供していたということだ。近代化という大きな流れのなかの避けがたいプロセスであるかのようなドクサは、どれだけ抗うことが難しいものであっただろうか。反射的に倫理的判断を下すことを躊躇わせるような状況が、想像を絶する強度で立ちはだかっていたはずだ。しかしライオンは、その状況で吠えたのだ。その過酷な状況のなかでの告発、抵抗、不服従は、ある意味でコモディティ化してしまっている、社会状況や世界の諸問題に言及しようとするアートを萎えさせることになるかもしれない。あらゆるものが、その孤高の行為の前では色褪せてしまう。
 シヴリ島。2015年、クリストフ=バカルギエフのイスタンブール・ビエンナーレで、ピエール・ユイグはこの沖に作品を設置した
シヴリ島。2015年、クリストフ=バカルギエフのイスタンブール・ビエンナーレで、ピエール・ユイグはこの沖に作品を設置した
2012年、クリストフ=バカルギエフのドクメンタのときのピエール・ユイグの作品
優生思想は、人間という生物の生死に人工的な手を加えようとする。もちろん、種々の医療行為も同じ性質を持つものだが、事後の光景は大きく隔たったものになる。医療行為の多くは、生半ばにして消えようとする命をなんとか存え、再び繁茂させようとするものだが、優生思想はそれを種々の条件で間引き、特定のものだけが生育する環境を人工的に造り出そうとする。この人為的な操作が生み出す整然さが、人を惹きつけてきたのだ。雑然とした繁茂を、整え、計画し、管理することの暴力。そうした力の原因、作用、そして結果は、本質的なかたちではあまり凝視されることがなかったのかもしれない。クリストフ=バカルギエフのドクメンタで印象に残っている作品がある。地図上のマークを頼りにカールスアウエを彷徨っていたのだが、なかなかそこに辿り着くことができなかった。そうこうしていると、片脚だけ鮮やかなピンク色の痩せぎすの白い犬が現れた。後を着いて行くと、あっけなく目的のものが目の前に開けてきた。美しいカールスアウエの光景を台無しにするかのように、建築や土木の資材らしきものが積み上げられ、地面も無造作に掘り返されている。山積された土砂の間に、作品らしきものの姿も窺える。頭部を蜂の巣で覆われた裸婦像だ。ドクメンタを伝えるメディアで繰り返しアイキャッチとして利用されたそれは、先述したユイグによるものだが、けれども彼の作品は、むしろその周囲にこそ広がっていた。放置された資材や山積された土砂、剥き出しになった地面、そして泥水を湛えた水溜り。それらすべてが彼の作品なのだ。せっかくの緑が、無残なかたちに切り裂かれている。その様子は、ありがちな露悪的なアートの所作のように見えなくもない。けれども考えてみれば、人間と自然の関係はそのようなものに過ぎない。整えられ、快適な緑を提供しているとはいえ、周囲のカールスアウエもまた、同じような行為が生み出したものに違いない。その行為が問われることがないのは、単に表面的な体裁がそうさせるだけのことだろう。ユイグのそれは、人間の行為そのものを露出させていた。
先に触れたイスタンブールの海底の作品においても、彼の姿勢は一貫していた。水面下6mにあるというそれを実見したわけではないが、資料などで見る限り、どう考えても海底に不釣合いな物質が無造作に置かれているだけで、カールスアウエの資材置場然とした状況と大きな違いは認められない。タクシム広場の集会に警察が介入した事件の影響で、クリストフ=バカルギエフのひとつ前、2013年のイスタンブール・ビエンナーレは、屋外でのイヴェントが軒並み規制されることになった。そのような状況で何ができるのか。国際展の意味についてクリストフ=バカルギエフと会話を重ねたというユイグが出した結論は、通常では実見不能な長期間のプロジェクトだった。同じような環境を利用しながら、一世を風靡したYBAのアーティストは、随分と安直なスペクタキュラーな作品を、今年、ヴェネツィアで披露している。もちろん、ユイグの作品においても、スペクタクルな要素は重要な役割を果たしている。けれども同時に、人間の行為と自然の関係を見つめるその姿勢は、人為的なものがあまねく優生思想的な世界に連続しているという告発と読めなくもない。ひょっとするとそれは、フォン・ガーレンと呼応してはいないだろうか。最初に足を向ける場所は、そうした想いが導いてくれた。
 マルルの町
マルルの町
グラスカステン・マルル彫刻美術館のジオラマ
しかし実際には、プレ・オープン前日の時間の余裕が、思いがけない経験をもたらしてくれた。隣町のマルルで、関連イヴェントとして、『The Hot Wire』と名付けられた展覧会が開催されていたのだ。過去のミュンスターの資料を集めたアーカイヴに加え、トーマス・シュッテとジョエル・ツアリンクスの作品もあるらしい。ミュンスターから列車で40分、さらに駅からバスで30分余り。町はミュンスターよりも小さく、歴史的な建物も目立たず、観光客の姿もほとんど見られない。静かな普通の生活が、淡々と営まれている。ミュンスターと比較すると中東系の人々が幾分多いだろうか。展示のあるグラスカステン・マルル彫刻美術館に向かう途上、いくつかパブリック・アートのようなものが目についた。美術館の入口の傍らには、どこかで見たような電話ボックスのような物体が置かれている。ジェームズ・タレルの「テレホン・ブース」だった。タレルの作品は日本でもいくつかの美術館に収蔵されているが、なかなか公開される機会に出合うことはない。しかしここでは、ずいぶんと無造作に、半ば放置されている。もちろん、重厚な扉を開ければ、タレルの視覚世界を体験することもできる。あまりにハードルの低い設置状況は、けれども、作品の内容とは別に、住民や美術館、行政の意識の高さを示しているようにも思われた。
過去の彫刻プロジェクトを、マケットなどを多用して振り返ろうとする美術館の展示は、懐かしいものや忘れていたものを想起させてくれただけでなく、時系列上の乱れを整え、散らかっていた情報を整理させてくれた。前回のドミニク・ゴンザレス=フォルステルの作品、過去の作品を縮小してアー湖の畔に設置したそれを、さらに小さくしたミニュアチュアのジオラマも展示されている。公共の空間とアートの関係、およびその変遷を考える上で、彫刻プロジェクトの歴史を振り返ることは意味があることだ。むしろ、常設であってもよいのかもしれない。美術館を抜けて裏手の庭園に出る途中にシュッテの作品があった。ミュンスターのアイコン、サクランボの作品とほぼ同じ形状で、頭上に戴く果物だけが西瓜に置き換わっていた。ツアリンクスの作品はその先の庭園のなかだ。200mの白線が庭のなかに延びている。毎朝、引き直されるという白線は、都市計画で移動が決まった建物に関係しているようだが、前回のパヴェル・アルトハメルが造り出した1kmの小径を反芻するかのようにも見えてしまう。いずれにしても、ミュンスターとの有機的な結びつきが巧みに演出されている。周辺地域の活性化を図ろうという思惑によるものだとしても、こうしたやり方なら悪くない。もちろん、マルルの町が独自に設置した作品も訪ね廻ることができる。しかし、注意して見ていくと非常に数が多く、かなり古いものもある。あらためてカタログで確認して驚いたのだが、マルルの町では、ミュンスターが始まる1977年よりも前から、積極的に公共空間のために立体作品を購入している。石炭鉱業と化学工業で隆盛したマルルは、1950年代から70年代のルール地方の近代化、ルールモデルネを象徴する町のひとつだ。1957年にはタウン・ホールの建設が立案され、国際コンペが実施されている。そのとき、歴史的モニュメント以外にパブリック・アートがないことが考慮され、プロジェクトの一部として公共空間のための芸術作品の大規模な購入が検討されたのだ。現在では恒久展示は100基前後にも達している。一方、彫刻プロジェクトは大半が一時的な設置で、常設は約40基に過ぎない。ミュンスターには極めて身近に先行例があったのだ。越後妻有の原型でもあるミュンスターだが、それもまた、まったくのオリジナルではなかったようだ。またここで興味深いのは、先行例であることを主張してもおかしくないマルルが、注目を集めるミュンスターのアーカイヴ担当という脇役に徹していることだ。いたずらに主張するのではなく、過去から蓄積してきたものを尊重し、自信を持って着実に更新し続ける。その謙虚さは、一時的な流行や注目度に流されない、市民の理解度の高さを示している。地域アート系のイヴェントに狂奔する日本の行政は、一時的な注目度や来場者数、経済効果だけでなく、こうした姿勢こそ研究し参考にするべきだろう。隣町の展示は、サテライトとして片付けてしまうにはあまりにも多くの内容を湛えていた。
 ピエール・ユイグ「After Alife Ahead」
ピエール・ユイグ「After Alife Ahead」
生活もまた自然の一部を構成していると考えるならば、パブリック・アートは、人為的な介入のわかりやすい例だと言えるだろう。事実、芸術作品が散りばめられたマルルの光景は、ユイグ的なハイブリッド性に包まれていた。ユイグへの気持ちが逸る。ミュンスターのユイグの作品「After Alife Ahead」は、他の作品とは少し距離をとるように、街の北部に孤立するように位置していた。元スケート場を利用したという会場に入ると、コンクリートの床面が切り裂かれ、またしても地面が露出し、地下水らしきものも浸み出し、ぬかるみ、水溜りもできている。建設作業の途上で放置されたような巨大な空間は、カールスアウエのそれと同じ印象に包まれている。中央に水槽らしきものが置かれ、時折唸るような低音が響いてくる。天井には開口部があり、定期的に天井の一部が下向きに折れ曲り、室内に突き出た羽根板の隙間から外光が射し入ってくる。その開閉と連動しているのだろうか、水槽のガラスが透明になり、束の間、水中の様子を覗き込むことができる。カールスアウエ的な光景に、シヴリ島沖の海底のイメージが重なってくる。巨大な空間の片隅には身を隠すようにキメラの孔雀が羽を休めている。カールスアウエ同様、微かな羽音を立てて蜂も飛び交っている。窓脇に並んだ鳩のシルエットも作家が意図したものなのだろうか。どこまでが作者の手によるもので、どこからが違うものなのかわからなくなってくる。指示に従ってダウンロードしたアプリも、何が正常な機能なのかわからず戸惑うばかりで、ひょっとすると液晶画面を覗き込む人々の姿をそこに登場させ、徘徊させたかっただけなのかもしれないとさえ思えてくる。荒廃したSci-Fi的な風景が、どこか前日のマルルの光景に重なり始める。ウィルスのように蔓延り、節操なく浸潤していく人間の所業。ユイグが凝視めようとする人間の姿は、アーティストを含む人間という生物全体の、ある種宿命のような、存在の仕方そのものなのだ。
クリストフ=バカルギエフのドクメンタの際には、ユイグと同じような性質を持つ作品はあまり見られなかったが、今回の彫刻プロジェクトではそれが多少浸透しつつあるのかもしれないという印象を受けた。例えば、駅裏の、旧市街とは反対側のクリスティアン・オツォックもそうだった。解体された地方金融庁の廃材を利用し、元の建物の記憶の再構築を試みる彼の作品は、そうした作者の意図とは別に、西側に広がる荒涼とした更地を眺めるための格好の展望台になっていた。ユイグよりも一般性には欠けるものの、けれどもむしろわかりやすく、人間の行為が払拭することができない破壊性を示していた。ミカ・ロッテンバーグのアジア雑貨の店舗に展開する「Cosmic Generator」も、2015年のヴェネツィア・ビエンナーレの延長上にあるものだが、生産の無軌道な暴力性を示している点では一貫している。タトゥ・ショップそのものを招来したマイケル・スミスの作品も、いまや地下鉄の車両やビルの外壁、店舗のシャッターよりもグラフィティで溢れかえる人間の皮膚を見せようとするものだが、街中を埋め尽くす人工的な処置の施された肌の様子は、まさにユイグの光景に他ならない。もちろん、ロッテンバーグのそれはドゥルーズ=ガタリ的な無意識のさらに深層で蠢く機械を示そうとするものかもしれないし、スミスのそれも、65歳以上の顧客に対して大幅に値引きするなど、アンダーグラウンドなイメージの文化との接続自体に意味を見出そうとするものなのかもしれない。けれども元スケート場で目にした光景は、それらの作品の本来の意図を容赦なく上塗りしてしまう。しかしもちろん、ユイグに卓見があると言いたいわけではない。そこには、おそらくユイグさえも感得できていない時代精神のようなものが関係しているはずだ。
 クリスティアン・オツォックの作品からの眺め
クリスティアン・オツォックの作品からの眺め
ミカ・ロッテンバーグ「Cosmic Generator」
まだ会期の残っている展示に対して言及する際、これからそこに出向く人の足取りに、可能な限り影響しないように心がけている。タブラ・ラサの状態でそこに佇んだときの感情や思考が、反芻するようなものに変質してしまったり、本来そこで生起されるはずのものが失われてしまうと考えるからだ。しかし今回、むしろ逆に、伝えようとしたことがあった。薦めたのはある経路だ。目的地は前回から10年以上継続しているジェレミー・デラーの長期プロジェクト。ほとんどの人は、手前にある彫刻プロジェクトのインフォメーションから向かうはずだが、反対側の入口から、遠回りして歩くことを薦めたのだ。ジェレミーの作品は、市民のための農園賃借制度、クラインガルテン(小さな庭)を舞台に、ラウベンピーパーという可愛らしい名前で呼ばれる、思いおもいのガーデニングや耕作を行う借主たちへのインタヴューや、彼らの日記を、それぞれ一冊の本にまとめて閲覧できるようにしたものだ。作家自身が手を入れた庭を進み、ガルテンラウベ、庭の展望台と呼ばれる所有者に建設が許された東屋に入ると、本棚に緑色の重たそうな本が収められている。そこには、庭に込められたそれぞれの想いが綴られている。しかし、もちろんそれは、頁を繰っても知ることはできるが、何よりも個々の庭に結実しているはずだ。遠回りして緑豊かな小径を通っていくと、両側にそうした庭々が連なっている。よく手入れされたものもあれば、放置されたような風情のものもある。ときおり、作業中の人が声をかけてくる。それらの庭の持ち主がデラーの協力者であるかどうかはわからないが、実際の対応関係は問題ではないだろう。さまざまな庭を楽しみながら、遠回りして小屋に辿り着き、重厚な本を開いてみる。しかしそのとき、ある意味でそれはすでに読み終えた書物になっている。
ドイツでは、19世紀中頃、産業化の進行する社会のなかで、人間としての生き方に疑問を抱き、生活改善を志した人々が都市近郊に入植し、自然との触れ合いを大切にした生活を試みるようになった。生活改善運動、レーベンス・レフォルムと呼ばれるそれは、一方では、現代の環境主義に連なる流れを生み出す土壌となり、他方、「血と土」のイデオローグ、リヒャルト・ヴァルター・ダレに象徴されるように、土への回帰は祖国に、そしてそこに住む民族へと結びつきやすく、20世紀に入るとファシズムという毒の花を咲かせることにもなる。クラインガルテンは、そうした入植運動と同じ動機を持つものだが、興味深いのは、ささやかな耕作や作庭が、意外なことに近代と密接に関係している点だ。しかし、余暇やリタイア後の時間を利用した今日のそれは、そう簡単に要約できるものではないのかもしれない。整然と区割りされたそこには、神経質過ぎるほどに整然としたものもあれば、お気に入りのバンドのロゴを掲げた、農園には似つかわしくないものまである。個々の区画の自由は、同時に、協調の放棄を意味してもいるのかもしれない。デラーの庭にしても、リヒターの立体作品のような鉄球が転がっていたり、ヨーダのような胸像が置かれたりしている。環境に対して意識が高いことや、自然に対する無償の愛を共有しているわけではなさそうだ。むしろ思いのままに改変できること、つまり、非干渉による自由こそがそこにはある。その意味では、クラインガルテンの光景は、どこかロッテンバーグの映像に通じているようにも思えてくる。ドゥルーズの無意識下の工場が、ロッテンバーグの雑然が、止めどなく生成し続けるもの。工夫を凝らした庭々が、突然、キッチュなアジアの雑貨店のようにしか見えなくなってくる。
 ジェレミー・デラーの庭とガルテンラウベ
ジェレミー・デラーの庭とガルテンラウベ
デラーの会場を訪れてから、気になっていたことがある。どこか軽い既視感のようなものに囚われたのだ。やがてその原因は、最初にミュンスターを訪れたときのフィッシュリ&ヴァイスの作品だということに気がついた。彼らが手を入れられたあの菜園は、まさにデラーの会場を取り囲んでいるクラインガルテンそのものだ。もっと早くそれに気づくべきだったのかもしれない。開幕前日に出かけたマルルで、パブリック・アートをいち早く導入したその町の光景に、カールスアアウエの資材置き場を思い浮かべていたのではなかったのか。そしてそのマルルこそが、ミュンスターに先行する原型でもあったのではなかったのか。だとすれば当然、ミュンスター自体がカールスアウエの不思議な風景に重なることになる。確かに常設された過去の作品は、ユイグの配した土木資材のように見えなくもない。人工湖にそそぎ込む流れのほとりに設置され、盗難によってむしろ知られるようになった荒川医の展示も、ギークたちの産廃のように見えなくもない。ミュンスターもまた、掘り返され、切り刻まれ、資材や廃棄物が放置された、人の手による無残こそが吹き溜まる場所なのかもしれない。
自然と人工の対比、あるいはそれらのハイブリッド。ユイグの光景は、もちろんそのまま環境における類似した状態を示すことになるが、例えば情報科学の進化による新たな知性の在り方、つまり人間こそが機械の一部として機能するような知識形態も想起させるし、あるいは、高度に進歩した先進医療が実現する管理の徹底した生命環境にも連続していく。そうつまりそれは、当然、優生思想に基づいた整理や管理という人為的介入が実現するはずのディストピアにも重なることになるはずだ。
ミュンスター市民の反発を恐れたとも言われているが、フォン・ガーレン司教の告発が奏功し、T4作戦自体はその直後に総統の口頭の命令で中止になっている。けれども、絶滅計画は密かに延命し、安楽死とカモフラージュされて、戦争末期まで継続していたことが知られている。中止命令を下した総統自身についても、精神的に頽廃している人間の表現を排そうとした暴挙から、T4、ホロコーストという流れを考えれば、その精神はむしろ流れを太くし、勢いを増していったと考えるべきだろう。しかし、表向きのものだとはいえ総統の命令を無視するまでして、T4作戦が継続できたのはなぜなのだろうか。その背景には、ドイツの精神医学界の、優生学的な考え方が大きく影響していたと言われている。おそらくここでの問題は、禍々しい第三帝国の首魁だけがその恐るべき計画を進めたのではなく、近代的な学究の精神こそが肯定的かつ積極的にそこに関わっていたということだ。すでに触れたように、優生思想そのものは19世紀末にはヨーロッパでは広く影響力を持っていた。T4作戦自体に限れば、その遂行は近代の精神自体が為したものとさえ言えるのかもしれない。極東の島国と比較すれば自省の姿勢が徹底しているドイツだが、驚くべきことに、精神医学関連の団体が当時の非を認めたのは2010年の総会のことだった。しかもその際、強制入院や拘束、不妊、断種などの処置に対しての謝罪はあったものの、組織的な絶滅処置に対して、直接、言及されることはなかった。しかしもちろんこれは、ある国の、特殊な組織の問題などではない。未だに忌まわしい行為自体を凝視できていないその姿勢は、近代の、わたしたち自身のものでもあるはずだ。
しかし一方、わたしたちはそうした悪夢のような状態から本当に抜け出したと確信してもよいのだろうか。ユイグの本意はともかく、彼のぬかるんだ会場で、指定されたアプリの挙動を確認すべくディスプレイの反射を顔面に受けながら、うろうろと彷徨う姿は、決して馴染みのないものではない。資材置き場のような、産廃処理場のような荒涼とした都会を、そうした人々がうろつく姿はむしろ日常でさえある。彼らの行動はあまねく、青白く仄光るディスプレイに統御されている。生活も、仕事も、恋愛も、健康も、すべてがある規範との対比によって管理されている。規制や管理は、生活の隅々まで浸透している。夜遅く、LWL美術館近くのカフェから帰る途中、吹き出してしまったことがある。横断歩道を挟んで反対側に、パンキッシュな身なりの若者の一群がいたのだが、その強がった仕草とは裏腹に、お行儀よく信号の指示に従っているのだ。車が通る気配は一切ない。確かに、自転車都市を宣言する街らしく、自転車に関しては法規も厳しく、自転車の警官が容赦無く罰金を徴収していく。それを怖れているのだろうか。彼らの反抗の身振りは一体何に対するものなのだろうか。信号の表示に一切関係なく、バイクも人も、車さえが隙あらば先に進もうとするアテネとは大違いだ。アテネから学べというのは、こうしたことを指しているのかもしれない。前回も触れた意地の悪い想いが再び脳裏をよぎる。
 田中功起の会場風景
田中功起の会場風景
ここまで触れて来なかった田中功起の展示で耳にした意見も気にかかる。田中の作品は、さまざまな文化的背景を持つ8人の住民たちとの9日間にわたるワークショップの記録で、水戸芸術館の個展を踏襲するものだったが、その結果は大きく異なるものになっていた。どこか同質な印象の参加者たちがぎこちない作業を重ねていく水戸の場合とは異なり、背景の異なる参加者がそれぞれの問題を開示し合う様子は、おそらく作家が本来意図していたものに近かったのではないだろうか。田中は、オープニングの前日、関係者向けのプレ・スクリーニングを行っているが、そこで耳にした、シナリオがあるものだと思っていたという意見が気にかかっていた。確かに、藤井光の上質な映像に加え、当日はワークショップの参加者たちも参加していたため、自分自身も一瞬、プロの役者が参加しているのではないかという想いに囚われたのを記憶している。水戸の場合、映像のなかで立ち上がるのは、田中を含めたファシリテータの人為的介入だったが、ここではむしろそうした印象は後退し、けれども逆に、映像全体を通して人為性が露出しているようにも感じられた。もっともそれは、田中の作品固有の問題というよりは、人間のコミュニティでの振る舞い方そのものに起因するものでもあるかもしれない。わたしたちは、規制され、統御され、管理された振る舞いのなかに閉じ込められている。そう考えた方が整合するような気がしてくる。そう理解するとき、田中の作品にもまたユイグ的な空気が漂うことになる。もっとも、人為的なものの無軌道や不恰好は、人間である限り逃れられない。そう考えれば、当然のことでもあるのだが……。
 第3回(1997年)、ハンス・ハーケの作品のあった遊歩道
第3回(1997年)、ハンス・ハーケの作品のあった遊歩道
冒頭で触れたハーケの作品は、反戦の意志を明確に示すものだった。市民たちに「尻の記念碑」と揶揄されるビスマルクの鉄血政策が引き起こした戦争の戦勝記念碑と同型の回転木馬を、厚い木板や有刺鉄線などで遠ざけたそれは、「戦争」を語源とするカルーセル、回転木馬の禁止であり、騎乗訓練機でもあったそれの拒絶を意味していた。また、どこで目にしたのか定かでなく、その後確認もとれていないのだが、普仏戦争などで疲弊した市民のために、戦争を忘れるための娯楽として回転木馬が導入されたことがあったという。もしそれが事実であれば、ハーケの作品は、戦争を忘却することの拒否という意味も持つことになる。隣接する戦勝記念碑の傍らで、強く示された反戦の意志。しかしハーケの作品の気配は、現在のミュンスターにはまったくない。これは彼の作品が、戦勝記念碑と物質的に呼応するサイトスペシフィックな作品だったためかもしれない。そのような作品にとって、作品の撤去はそのまま忘却を意味しかねない。もちろん、彼の作品の本意は、当然、ビスマルクの戦争だけを対象とするものではない。けれどもその物理的な係留が、むしろそれを矮小化し、忘却を許すことになる。回転木馬の記憶は、もっと拡張されなければならない。
ユイグの作品が呼応しているのは聖ランベルティ教会ではない。ライオンの咆哮という記憶であり歴史だ。しかもその呼応は、ある特殊な時代の、勇気ある告発としてしか理解されてこなかった出来事を、別の文脈に接続するという意味も持っている。しかもそうすることで、超克してきたと思われていた問題が、現在もなお、かたちを変えて継続しているかもしれないという可能性にも気づかせてくれる。総統が禁止を命令したにもかかわらずT4作戦は継続し、予行の役割を果たしたかどうかは定かでないが、より徹底した絶滅作戦へと発展していく。事後の贖罪に関しても、一応の身振りは示されたものの、ドイツ精神医学界の対応の遅れと、不徹底には釈然としない想いが残る。フォン・ガーレンの勇気ある行為は、無視され、蔑ろにされたのだろうか。ミュンスターにもその徴は残されている。ヨーロッパ各地から絶滅収容所に送られたユダヤ人の記憶を留めようとするギュンター・デムニヒの「躓きの石」は、彫刻プロジェクトの古都にも数多くある。それはまぎれもなく、司教の努力にもかかわらず、水面下で物事が進行してしまったことを示している。しかし、彫刻プロジェクトの地図を手にした人々はそれに気づくこともなく、聖ランベルティ教会を見上げることもほとんどないだろう。政治や社会の問題に高い意識を示しているはずのアートに関わる人々は、皮肉なことに、足元の歴史や記憶を気づくことなく、踏みつけながら次の目的地に急ぐことになる。アートはそれ自体、ウンベルト・エーコ風にいうならば生産者も享受者も、ユイグ的な光景のなかで蠢くばかりの存在に過ぎないのかもしれない。忌まわしい時代を乗り越えたつもりの人々の住む街は規制に溢れかえり、情報の爆発的膨張の只中で人々はモニターを見入らないと食事の場所も決められない。若者たちは信号の色が変わらないと行きたい場所に進むことができず、健康被害という脅迫が、第三帝国以上の厳しさで喫煙者を追い立てる。経済活動からはじき出された人々は路上で気まぐれな善意をあてにしなければならず、裕福とされる国々は他国の懐事情にまであれこれと口を出しプライドまで引き裂こうとする。司教の抵抗は、確かに蔑ろにされたのかもしれない。けれどもユイグの空間と呼応することで現代に連続し、当時と変わらない切実なものとして再び迫ってくるとき、問われているのは、わたしたちが再びそれを蔑ろにするかどうかということのはずだ。
 アレクサンドラ・ピリチ「漏洩領域」
アレクサンドラ・ピリチ「漏洩領域」
足元の「躓きの石」を気にかけながら、聖ランベルティ教会に向かって伸びるローテンブルク通りをしばらく行くと、右手に旧市庁舎があり、1648年、ヴェストファーレン条約の調印が行われた部屋が残っている。フリーデンサール、平和のための講堂と呼ばれるそこで、アレクサンドラ・ピリチの「漏洩領域」と題されたパフォーマンスが行われていた。マニフェスタ10の際のパフォーマンスの延長上にあるそれは、歴史的な結節点となった空間にいながら、歴史上の出来事を身体で彫刻化することで時空を行き来してみせるだけでなく、最後にはそれが、情報空間に散逸していくまでを示そうとしていた。具体的な事例を深く掘り起こそうとする作品の多くは、それぞれの歴史、出来事の疑いようのない固有性にもかかわらず、ある種のコモディティ化のなかに沈み込んでしまう。あるいはその固有性ゆえに、新たに分断が生まれることへの配慮に欠ける場合もある。ピリチのような柔軟な姿勢は、個々の問題に対する踏み込みは不十分かもしれないが、実際的かつ具体的な対応関係が陥りやすい、硬直と忘却の危険から抜け出すためのひとつの可能性なのかもしれない。あるいはその柔らかいネットワークは、分断を回避するためのある種の視座を与えてくれるのかもしれない。同じように、ユイグ的な空間とフォン・ガーレンの呼応、そしてそれがミュンスターを、世界を被覆しているのではないかという妄想もまた、ある出来事を固有の係留から解き放ち、今日的な再解釈のなかに解き放つのであれば無意味なことではないはずだ。本来距離のあるはずの出来事間の曖昧な呼応は、近代的な言表領域からはみ出そうとする過剰でもある。ビフォの『蜂起』によれば、詩的過剰は抽象性の高い敵に対する有効な対抗手段でもある。物質や歴史的事象との具体的係留を解消し、より多くの係留点を見出そうとする妄想は確かに過剰でもあるだろう。係留点はいたるところに現れ、個々の係留地に縛られていた意味は拡張される。国際展に関しては、キュレーションの在り方が問われる傾向が強い。しかし、それ以上に問われなくてはならないのは、そこを訪れる享受者の側の過剰であり妄想なのかもしれない。
 ミュンスター旧市街のギュンター・デムニヒ、「躓きの石」撮影:湯浅千紘
ミュンスター旧市街のギュンター・デムニヒ、「躓きの石」撮影:湯浅千紘
ナノソート2017
no.1「シンタグマ広場に向かう前に……」
no.2「アテネ、喪失と抵抗の……」
no.3「ミュンスター、ライオンの咆哮の記憶……」
no.4「愚者の船はどこに向かうのか……」
no.5「幸せの国のトリエンナーレ」
no.6「拒絶、寛容、必ずしもそればかりでなく」
no.7「不機嫌なバー、あるいは、政治的なものに抗するための政治」
no.8「南、それは世界でもある」
杉田敦|Atsushi Sugita
美術批評、女子美術大学芸術文化専攻教授。主な著書に『ナノ・ソート』(彩流社)、『リヒター、グールド、ベルンハルト』(みすず書房)、『inter-views』(美学出版)など。オルタナティヴ・スペース art & river bank を運営するとともに、『critics coast』(越後妻有アートトリエンナーレ)、『Picnic』(増本泰斗との協働)など、プロジェクトも多く手がける。4月から1年間、リスボン大学美術学部の招きでリスボンに滞在。ポルトガル関連の著書に、『白い街へ』『アソーレス、孤独の群島』『静穏の書』(以上、彩流社)がある。
