身体と名前のアレゴリー
インタビュー/アンドリュー・マークル
I. 規律が生み出すズレ

Installation view of the solo exhibition “Chronochromes, Data, Motifs” at Rat Hole Gallery, Tokyo, 2011. All images: Courtesy Cheyney Thompson and Rat Hole Gallery.
ART iT 以前、あなたとアートの教育カリキュラムや異なる価値体系を持つさまざまな文脈を横断するアートについて話しあったとき、あなたは「常に経済モデルに関心があり、(ビジネスマニュアルみたいに聞こえるかもしれないけど)なによりもまずグローバルマーケットにおいて役立つ、経済モデルの関係性、さらにはその種の知識の構造に関心があるが、一方ですべての活動を正当化するのに有効な物語へと簡単には落とし込めない、公の歴史の外側に位置するものがある」と言っていましたよね。グローバル化した世界においてマーケットはアイデンティティである、と考えてみたらどうでしょうか。つまり、すべてのものがグローバルに流通しているとしても、マーテットそれ自体は非常にローカルな状態のままに留まる。だからこそ、マーケットはアイデンティティになりうるとは考えられませんか。
チェイニー・トンプソン(以下、CT) そうですね。関係性の美学のある側面は、マーケットで流通する上で理想的なものかもしれません。そのアイデンティティは拡散していくにもかかわらず、どこであろうが同じものである。つまり、企画され、参加するという民主的な形式の自立共生の表明として現れます。もちろんこれは、今ではいくらか下火となったこのカテゴリーに括られるすべてのアーティストに必ずしも当てはまるわけではありません。例えば、そのはっきりとした敵対的アプローチのために、サンティアゴ・シエラを例外にしたいという誘惑は常に存在します。しかし、そこにはあなたは決して交通手段が原因で身動きがとれなくなったり、タトゥーを彫られたり、壁の前で座り続けさせられないという安心感のようなものがあります。この参加するかしないかという見せかけの選択が備わっているという安心感、まるでわたしたちに選ぶ権利があるという錯覚が、この作品をグローバルなアートの消費の論理に結びつけているのだと思います。
しかし、個人的にはこうした問題との関連でアイデンティティの問題を提起することが重要だと考えています。自分自身が抗いたいというなにかが、アイデンティティなのではないでしょうか。包括的であれとも、マーケットと完全に一体化したような超均質性を獲得せよとも言ってはいません。前提とされたマーケットという社会的関係性におけるアイデンティティが理想的なのではなく、同じものの外観には常に他者性や相違点が存在していることを自覚すべきなのです。そうでなければ、アイデンティティについて話すことなどできないし、我々は空気や空っぽの空間かなにかと同じようなものになってしまう。
ART iT 少し唐突な質問ですが、自分自身のことをアレゴリーに意識的なアーティストだと思いますか。
CT アレゴリーについてより深く理解していれば、そういえるのですが。ヴァルター・ベンヤミンも読んだし、アレゴリーがどのように機能するかについて、少しは知っているつもりですが、もっと知っていればと心の底から思います。いや、ふざけているわけではありません。例えば、アレゴリーが言語の特殊性に満ち溢れた形式だとしましょう。あるやり方でわたしがテーブルに置いたスプーンを、あなたがなんらかの意味として理解する。そして、別の誰かがそのテーブルに近づいてきて、その人はあなたが受け取った意味は知らないにも関わらず、それでもなぜか、スプーンの配置を認識することができてしまう。わたしはアレゴリーをこのように理解しています。どういうことかといえば、言語が複数の文脈を移っていき、言語自体を記述できなくなる推移のことをアレゴリーだと理解しています。その意味で、わたしは形式や歴史や言語行為の布置はすべて、ある正しい瞬間に結びつき、その後、潜在的に失われていくのだということに対して意識的です。
ART iT マンセル表色系を時間を計測する方法へと、また絵画自体を労働時間の記録へと変換した抽象画「クロノクローム」や、建築の構成要素についてのトロンプ・ルイユ(だまし絵)のインスタレーション作品「1988」(2004)はアレゴリーの一例といえますか。
CT その通りです。かつて制作した折り畳み式テーブルの絵画でさえもそうです。ちょうどベンヤミンを読み始めたころに制作をはじめたので、露天商をある種のアーケードが老朽化したものとして見ていました。そして、もしわたしたちがアレゴリストならば、そこにあるきわめて小さなものの配置が示すなにかを解釈できるのではないかとも考えていました。しかし、歴史が避けられない運命として生産される傾向を帯び、媒介物が不明瞭な意味を予知するものへと還元される範囲において、わたしたちはアレゴリーの欠陥に直面する。

Installation view of “Quelques Aspects de l’Art Bourgeois: La Non-Intervention” at Andrew Kreps Gallery, New York, 2006.
ART iT アレゴリーという言葉を持ち出したのは、今回のインタビューにあたり、あなたの作品を見たり、作品について書かれたものを読んでいるときに、ピエル・パオロ・パゾリーニの『ソドムの市』(1975)を思い出したからなんです。もちろん、パゾリーニの堕落した性に対するグロテスクな演出と、表面上は非常に抽象的で落ち着いた絵画、彫刻、インスタレーションというあなたの作品は異なります。しかし、どちらの作品においても、その表面は実際とは裏腹に内在する底意を隠しているのではないだろうかと思いました。
CT その比較はおもしろいですね。おそらく、原作以上にグロテスクなパゾリーニの『ソドムの市』よりも、その原作者、マルキ・ド・サドの『美徳の不幸』(1787)みたいなものに親近感を感じます。それらは形式上、繊細に綴られた美しい倫理的な物語にも関わらず、実際には抑圧や支配がきわめておぞましいものとして暗示されています。
例えば、私のマンセル表色系の使用法は色彩の合理性を称賛するものでは一切なく、いかなる統括された合理的な枠組みが、どのように全体として機能する場所へと必然的に配置されるのかに使用されています。それはひとつの統制の手段なのです。洗練されていようが、対称的もしくは非対称的であろうが、それがなんであれ、法則としてそこにあることに対し、疑問があるのです。例えば、バッハは非常に美しく、理性的な音楽を作曲しましたが、その曲を演奏し、実現するためには厳格な規律が必要とされます。その曲の理性的な構造に順応出来る身体が必要とされるのです。そうした推移、計測の論理に対する身体の模倣的反応こそがわたしの作品の核となる関心事のひとつです。
ART iT それはあなたにとって、ほとんどマゾヒスティックな追求だといえませんか。
CT そうですね。それは個人的な性格みたいなことかもしれないし、そうではないかもしれない。ジョージ・ベイカーが「Long Live Daddy: A Dada Montage」というダダに関する非常に優れた文章を、著書『The Artwork Caught by the Tail: Francis Picabia and Dada in Paris』(MIT Press, 2007)のエピローグとして載せています。口論のような形式で書かれていて、正確には思い出せないのですが、要するにベイカーはダダイストをマゾヒスト、フロイドの理論や知識を用いて、中流階級を非難したシュルレアリストをサディストとして特徴づけています。彼によれば、言語の崩壊が吃音による詩へと向かうところへと、ダダイストは日常の暴力性を内在化させていました。ほかにもピカビアが自らを撮影し、そのプリントに描きなぐり、切り刻んだセルフポートレートの例を挙げています。これらすべてはアーティストの身体上で表現されています。
ART iT そういう意味では「1998」はサドマゾ的といえるのかもしれません。巨大かつ正確な絵画のインスタレーションを遂行するマゾヒズム。それはギャラリーの中央に設置されたバリケードに邪魔され、作品の完璧な姿を見ることができない観賞者へと伝わっている。
CT 確かにそうですね。おもしろいのは、制作した頃よりも最近の方があの作品についてよく考えているということです。ある意味、とりわけ「1998」を発表したあの展覧会では、遠近法の歴史や一般的な歴史というそれまで考えてきたことを一度止めてみたんです。伝統的な遠近法はセザンヌやキュビズムによって乗り越えられたのだと言われてきましたが、ビデオゲームから建築デザインに至る新しいテクノロジーの台頭とともに、今日、遠近法は、見たところ無批判に、表象の主要な形式として再浮上しています。わたしにはそれがコンピュータを簡単にドローイングツールとして使えることからくるのか、それとも文化的に、固定され、安定した”見る主体”への回帰が必要とされていることからきているのかわかりません。しかし、アイデンティティや非アイデンティティについて考えるとき、主/客、自己/事物、思考/世界、自然/歴史の差異、それがなんであれ、最初のアイデンティティは差異から経験するということは間違いないと思います。それが最初の心的外傷の分裂です。「1998」では、ギャラリーの中央にバリケードを置くことで主体の居場所を消し去り、あなた自身のものの見方、つまり、あなた自身、判断できる独立した主体としてのアイデンティティやその完全性を一時的にでも事物の世界と区別できなくなるよう試みました。わたしたちはただ名付け、分類し、「わたしがこれを見ている」と言えるような存在というよりも、物質としてのわたしたちという物質文化に直面しなければいけません。これは、新たな主体を構成するために主体を一度破棄するという、わたしが作品を考える上での方法論的持続かもしれません。
ART iT アイデンティティと言えば、マーケットで作品を扱うという再帰的な過程へとあなたを導いたものはなんですか。
CT ある部分では反抗的な10代を過ごした経験が関係しているかもしれません。わたしは80年代後半と90年代を大きな失望の連続として経験しました。ある一定の政治意識が芽生えたのが、1990年、14歳の頃だと思います。それがなんなのかはわかりませんでしたが、なにかが終わり始めていると認識していたのです。89年から90年にかけて、メディアスペクタクルとしてのアースデイの再来と共産主義の挫折という一対の出来事が起こりました。漸進的な政治が強引なマーケティング技術と一体となっていくという経験に絶望のようなものを感じたのを覚えています。おそらくこれがマーケティングツールとしての企業責任と呼ばれるものの発端なのでしょう。もちろん、その頃まではある種のインディペンデントの価値を残していた音楽業界にも、80年代のさまざまなアンダーグラウンドの整理統合を通して、同じようなことが起こりました。
わたし自身の人生がそこまで悪いものだったとは言いませんが、いろいろなことが90年代へ向けて悪い予感をもたらしていたのです。大学の社会主義学生連盟への参加も失望だらけでした。わたしがそこを気に入っていたのは、なにか生の歴史や伝統的な思考に加わることができるという点でしたが、あの時期はずっと、政治的に物事はとにかく崩壊しているように感じていました。そして、90年代も終わりに差し迫った98年に、理論上は完全に独立しているアーティストランスペースの立ち上げに関わりました。出来る限りプロフェッショナルにやりたかったのですが、結局、必死に働き、総力をかき集めるポトラッチ的手法をとって、組織自体もそうした精神を反映したものになりました。つまり、作品も売らない、わたしたち自身やスペースに関する宣伝すらしない。当時、アーティストランスペースに対する需要が高まってきていて、ある意味不完全で組織されていないわたしたちのスペースは、マーケティングを重視し、メインストリームの外側で収入を得る方法を探しながら、その「外側」を直ちに消費可能なものとしてブランディングしたいニューヨークのアレッジド・ギャラリーのようないわゆるオルタナティブギャラリーに対するカウンターポイントとして必要なものだったのです。

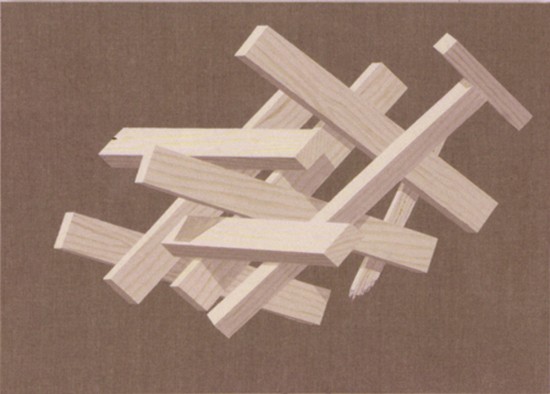
Top: Installation view of “1998” at Andrew Kreps Gallery, New York, 2004. Bottom: From 1998 (2004), acrylic and oil on linen, approx 61 x 86 cm.
ART iT それでは「1998」はマーケットに言及した作品であったといえますか。
CT ある意味ではそうでしょう。未だに全体像を描けてないということはありますが。最初にいくつかのトロンプ・ルイユの絵画を制作した後、アンドレア・クレプス・ギャラリー(ニューヨーク)での初個展の準備のために2001年から翌2002年まではその制作を中断していました。最後に制作したのは2003年か2004年です。わたしにとって、伝統的な遠近法は資本主義の組織を補完するものです。主体は常に消失点、つまり、決して辿り着けず、一定の距離から見ることしかできない神秘的な一点との関係性によって世界に布置されます。言うなれば、これは商品崇拝に対する優れたアレゴリーです。欲するものは見えても、その社会関係や労働は見ない。それらは消失点の反対側にあるのです。労働と経済のある種の関係性におけるグローバルな施行を前提としたとき、このような表象の形式が、従来、そして現在の特権的な立場を享受することも理解できます。
ART iT しかし、遠近法的にものを見ることさえも資本主義のシステムに条件付けられており、そうしたシステムにおいては実際のところ、非遠近法的視点の方が現実の状況に近いのではないでしょうか。
CT その可能性もありますね。それは表象と現前の違いであり、印刷機とルネッサンス絵画の違いかもしれません。絵画は遠近法の使用を通して、実在する社会関係の秩序を保持し、再生産する。それに対し、印刷機はそのような関係に抗い、豊富な教養と近代デモクラシーの起源を準備します。おそらく読むことと遠近法的に見ることの間に違いを見出すことができるかもしれません。もちろん主体のアイデンティティを再生産する書き方というのは存在しますが、批判的な修正を経験させる書き方というのも存在するのです。
初期作品では、遠近法の再帰を批評的に考えたいという状態に囚われていていましたが、作品を展開させていくなかでは、批評したいと考えていたその問題を再生産することしかできませんでした。それこそ、ちょうどあなたが言ってくれたような、わたしの作品におけるサド・マゾヒスティックな要素なのでしょう。当然、遠近法によって組織された150点もの絵画作品を見せれば、スペクタクルは生まれるでしょう。そうしたものを作ることさえ、わたしには苦痛だったのです。
チェイニー・トンプソン インタビュー
身体と名前のアレゴリー
I. 規律が生み出すズレ | II. ロベール・マケールというインデックス »
