
2010年5月、第17回シドニー・ビエンナーレにて発表されたアイザック・ジュリアンの新作映像インスタレーション作品『Ten Thousand Waves』は2004年にイギリス北西部モーカム湾での中国人不法移民の事故-貝を採集しているときに波にさらわれた-を題材としている。イギリス国内での不法移民ビジネスの存在が明らかになり、当時注目を集めた事故である。
張 曼玉(マギー・チャン)、趙濤(チャオ・タオ)と人気女優をキャストに、楊福東などをスタッフに加えて製作されたこの作品はこれまで主に自身の出自である黒人文化やアフリカ植民地主義に焦点を当てたものから、中国という直接的には自身のルーツと関係のない国の出来事を扱うことで、これまでのアプローチとは違う側面を見せる非常に興味深い作品である。
ART iTは、シドニー・ビエンナーレのオープニング後、中国、上海でのプレミア上映となったシャンアート・ギャラリーでの個展の際に、ジュリアンへのインタビューを行った。ポスト・コロニアリスムの作家として注目を集めてきたアーティストが試みる新たなパラダイム転換とはなにか。
(1) 奇跡とまごう符牒
作品とポストコロニアル理論とクエンティン・タランティーノの関係について

Installation view of TEN THOUSAND WAVES (2010) at ShanghArt, Shanghai, 2010. Nine-screen installation, 35mm film transferred to High Definition, 9.2 surround sound, 49 min. 41 sec. Photo Adrian Zhou, courtesy of Isaac Julien and ShanghArt Gallery, Shanghai.
刘芝芳、於彗
死者の数はわかっている
ニューヨーク州ロッカウェイ 23人
イギリス、ドーヴァー 58人
中国深圳 18人
韓国 25人
他でもたくさん
手段もわかっている:歩いたり、泳いだり、飛んだり
金属コンテナ、トラックの荷台、船の貨物室
どう死んだかもわかっている:餓死、強姦、脱水、溺死、窒息、ホームシック、心臓病、過労死、過労死
我々も同じ運命に至るかも知れないとわかっている
『Ten Thousand Waves』のための王平 “Small Boats”から抜粋
ART iT これまでの作品は『Vagabondia』 (2000)、『Paradise Omeros』 (2002)、 『Fantôme Créole』 (2005)、そして『Fantôme Afrique』 (2005)など、ポストコロニアル感覚を表現したものといえますが、新作『Ten Thousand Waves』においてポストコロニアルを脱し、中国に来るとどうなるのでしょうか。作品準備中にこの点をいろいろ、考えたのでしょうか。
アイザック・ジュリアン(以下I J) 2004年に『Ten Thousand Waves』のためにリサーチを始めました。その後2007年に、高士明、ジョンソン・チャンとサラト・マハラジがキュレーターとしてオーガナイズした第3回広州トリエンナーレの公開討論会に、キュレーターのマーク・ナッシュが出席者として招待された際、私はプロジェクトのリサーチ旅行の一部に参加しました。討論会とトリエンナーレのテーマは「ポストコロニアリズムへの告別」で、中国に来て、ポストコロニアリズムというパラダイムによる構造を拒否するという再調整は大変に興味深かったです。このパラダイムを否定するのは正しいことであり、大変に教育的で、多くの疑問を検討するチャンスとなりました。逆に『Ten Thousand Waves』へのアプローチを再び可能にしました。
1990年代初頭のロンドンでは、英国文化研究、ポストコロニアル研究と精神分析学、デリダなどの面白い交わりがあった時期があり、多くの理論が出回りました。文化理論とそのビジュアルアートにおける表現の絶頂期で、一般からの関心も高まり、私も『Creole and Creolization』のプラットフォームである『Paradise Omeros』の展示で参加した、オクウィ・エンウェゾーのドクメンタ11でクライマックスを迎えたと言えます。
『Paradise Omeros』『True North』(2004) 『Fantôme Créole』といった私の作品はポストコロニアル理論の議論をアートに変換しようとしたものの、一方では、同時に作品と一部の批評家によるポストコロニアル的価値観に基づく狭い解釈との間に緊張が生まれました。ポストコロニアリズム理論が西欧の覇権、または他者との関係の構造パラダイムであり、中国的な視点からするとフラストレーションを招くものであることは理解できますし、私自身フラストレーションを感じることがあります。
しかし、サラト・マハラジが広州についてのエッセイで指摘したように、それを否定するのは簡単なことではありません。2度目の訪中時、幾つかの大学を訪問しましたが、何人かの中国文化研究者がポストコロニアルや文化研究の理論を自らの研究に利用していると述べていました。特にニューヨークでは、世界中のビエンナーレに対して、「あちこちでビエンナーレがある」との文句を耳にしますが、英国における文化研究の言説は、異なったモダニズムがあり、西欧との異なる交渉があることを認識するために重要な役割を果たしているのです。世界各地のアートのなかで、ひとつの例はスチュアート・ホールの仕事です。「他のあらゆるところ」からのアイディアと情報に対して最も受容力があるのがこの理論ですが、なぜポストコロニアル研究は議論されるパラダイムでありうるのか完全に理解できます。
ART iT でも「他者との関係の構造」という点において、もし西欧の観点から客観性を築くことを意識しないのであれば、ポストコロニアル的観点は無意味になるのではありませんか。
I J 全くその通りです。でも、西欧の観点がいわゆる東洋においてまったく無意味と言えるでしょうか。「ポストコロニアリズムへの告別」と本当に言えるでしょうか。 友人がかつて私に言いました。「ポストコロニアリズムよ、さようなら。マーケットよ、こんにちは」と。上海に殺到しているインターナショナルブランドの広告を観てご覧なさい。特に私はアーティストやフィルムメーカーとしてイメージを扱っていますから、中国が西欧の注視から完全に自由であるかどうかは確信できません。こういう西欧のイメージが出回っていることを観ると、そこにはイメージと関連した優位的な主観性があり、それは無視できないほど強いと思います。これは、私のようなアーティストにとって探るべき余地、イメージの心理的空間です。
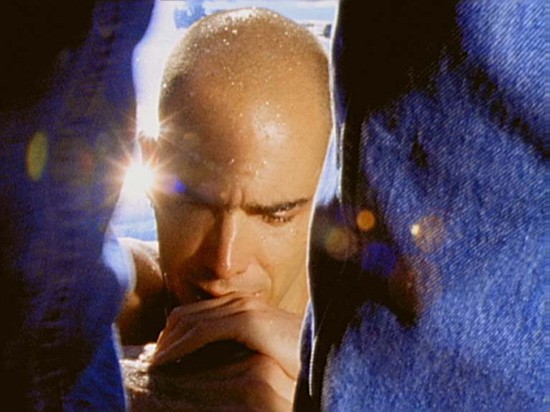

2点とも: Untitled (from Mazatlán) (2001), Duratrans in lightbox, 51.5 x 39 x 12.5 cm. Courtesy of the artist and Victoria Miro Gallery, London.
ART iT アーティストになり始めた時、ポストコロニアル理論はインスピレーションだったのでしょうか。作品の構造に積極的に活用したのでしょうか。
I J もちろん。『Territories』(1984)や『Looking for Langston』(1989)のような初期の映像作品はそれなしには作れませんでした。仲間に従って、スチュアート・ホール、ガヤトリ・スピヴァク、ポール・ギルロイ、リチャード・ダイアー、そしてもちろん、ホミ・バーバーの有名なエッセイ 「The Other Question」(1983) を読みました。それから1988年には、文化芸術評論家コベナ・マーサーと一緒にスクリーン誌の論説員を務めました。でもポストコロニアル理論だけにとらわれていた訳ではありません。フィルム理論や精神分析、そしてこれらの思想をメディアで表現することに関心がありました。1995年のロンドンの現代芸術研究所の『フランツ・ファノンと映像表現』会議出席はとてもエキサイティングでした。ちょうどマーク・ナッシュ(スクリーン誌の編集者でドクメンタ11のキュレーター)と共同で映像作品『Frantz Fanon: Black Skin White Mask』(1996)を制作中だったのです。スティーブ・マックイーンが初めて参加し、グレン・ライゴンやローナ・シンプソンといったアーティストも、会議と同時開催の展覧会『Mirage: Enigmas of Race, Desire and Difference』に参加していました。思い返せばコンセプチュアルブラックアート運動が形成されつつありました。「ポストブラック」と言ってもよいかもしれない。違ったニュアンスがあり、異なった表現に発展して行きました。
しかし、もちろんアーティストとして異なった方向に展開し、他の議論とも関わりたい。1999年には『Long Road to Mazatlán』というフィルムインスタレーションを制作しました。表面的にはアメリカ西部の2人のカウボーイを扱った作品で、ターナー賞にノミネートされました。あえてウォーホールっぽくした作品で、ポストコロニアリズム的パラダイムに対してすでに挑戦していたと言えます。2人の白人らしい主役を使いましたが、ひとりは私のプロジェクトに協力してくれた、振付師兼ダンサーのJavier de Frutosです。当然、彼らをゲイとして、欲望をウォーホール的に扱い、ポップ・アートの要素を引用しましたが、すでに意識的にポストコロニアル的予想をひっくり返そうとしていたのです。これを観た友人の中には「君が作るなんて変だよ」と言う人もいましたが、「これこそが私の主眼だ」と思いました。
とは言え、ポストコロニアル的状況は私の作品のテーマのひとつと言えるでしょう。でも関心があるテーマはこれだけではありません。残念ながら、これは全ての人の視点ではありません。
ART iT 作品において、個人的、非理論的、無理論的な部分はどれくらいあるのですか。ご自身の家系との関係、『Paradise Omeros』の舞台となったカリブ海のセントルシアとの関係とか。
I J 私の作品には明白な形と限らずとも理論的思想がたくさん、盛り込まれています。作品を制作する場合、理論的思想を別の形態で表現したいから、詩はとても重要だし、音や色や「パラレル・モンタージュ」といった道具を美的に利用したいのです。「パラレル・モンタージュ」とは私の編集者アダム・フィンチと私が開発したもので、従来の映画の厳密なリニアを編集したというより、一度に幾つかのスクリーンをひとつの建築空間に編集したものです。この形式的な要素は他のテーマと同等に重要なのです。しかし、評論家によってほとんど議論されていません。おそらくポストコロニアル的状況について話すことのほうが容易だからでしょう。
だから、私の作品には必ず、テーマと美的戦略の対話がありますが、美的戦略は作品自体を超越して、別の対話を始めるわけです。『Mazatlán』はパフォーマンスアートと西部劇映画の構造に関する対話です。『Ten Thousand Waves』は1930年代の上海映画に関する対話、または上海在住のメディア・アーティスト楊福東のコンテンポラリーインスタレーションに関する対話なわけです。言い換えれば、国境を越えた一定の内省が私の作品にはあると思っています。

Installation view of Baltimore (2003) at the 3rd Berlin Biennial, 2004. Triple DVD projection, 16mm film transferred to 3 DVDs, 5.1 Sound, 11 min. 36 sec. Courtesy of Isaac Julien and Victoria Miro Gallery, London.
ART iT 映画界ではクエンティン・タランティーノが、他のジャンルとの対話、あなたと似ている内省的アプローチで知られています。タランティーノの映画は観ていますか。それとも単に偶然に似ているのでしょうか。
I J タランティーノのことは崇拝していますが、同じ内省的アプローチを用いているかどうかはわかりません。私はドキュメンタリー『Baadasss Cinema: A Bold Look at 70’s Blaxploitation Films』(2003)のためにタランティーノにインタビューしました。このドキュメンタリーは1970年代の黒人アクション映画に関するなかなか皮肉だけど、ちゃんとリサーチした映画エッセイだったのです。このリサーチはその後の作品『Baltimore』 (2003)に広がりました。『Baltimore』は未来的SFブラックスプロイテーションのメディア・インスタレーションでした。クエンティンとの最初の対話は彼に対するオマージュと言えるもので、実際、古典的作品『Sweet Sweetback’s Baadasssss Song』(1971)を監督した黒人アクション映画監督で俳優のメルヴィン・ヴァン・ピーブルスと一緒に『Baltimore』に、出演して欲しかったのです。でも同時に、私自身はまったく、他の人とは違うと思います。そして、クエンティンもまた私とまったく違うと思います。
ART iT 『Baltimore』のアプローチが皮肉でリサーチされたものだとしたら、作品で取り上げた内容と同一化する試みは排除するということでしょうか。
I J 『Baltimore』は長時間のリサーチに基づくものです。2000年から2002年にかけて、私はハーバード大学で 「ブラックスプロイテーション・シネマからクエンティン・タランティーノまで」という授業を教えていました。学生と議論したり、彼らに作品を見せることで、構想を練り始めたのです。私の作品は、黒人アクション映画の反対というか、対極にあるものです。ステレオタイプを否定、あるいは再表現することによって隠された記号をあらわにしたいのですから。
しかし、『Baltimore』を制作することによって―これは 『Mazatlán』にも関連しているのですが―表現を誇張して引き合いに出さなければ、なかなか生きていけないということに気づきました。いくら差別偏見がないように行動しよう、差別偏見を否定しようとしても、我々はある程度、どうしても記号にとらわれているわけです。ジュディス・バトラーと彼女の脱・同一化に関する著作のことを念頭に置いているわけですが、動くイメージ文化のメカニズムや装置でこれらは作用しているわけです。
『Baltimore』には、同一化というより、脱・同一化が描かれていますが、ビデオアートで1970年代の黒人アクション映画の比喩を再現することで、その比喩を扱った作品なのです。映画の道具や戦略の歴史を利用することや、私が「ポストシネマティックビデオアート」と呼ぶ芸術的なコンセプトのために映画の想像力を適用することに私が関心を持っているという点において作品は映画的です。
 Isaac Julien and Sunil Gupta – Homage Noir (Looking for Langston Series) (1989). Courtesy of Isaac Julien, Sunil Gupta and Victoria Miro Gallery, London.
Isaac Julien and Sunil Gupta – Homage Noir (Looking for Langston Series) (1989). Courtesy of Isaac Julien, Sunil Gupta and Victoria Miro Gallery, London.
ART iT 『Baltimore』には明らかにアンビバレンスがうかがえます。称賛なのか、批評なのか疑問を抱きますから。また初期の作品『Looking for Langston』 (1989) は、ハーレム・ルネッサンスの詩人ラングストン・ヒューズの称賛と言えますが、彼の性的指向についてヒューズの遺産管理人と論争となりましたね。
I J その通り。黒人カルチャーと対話する映画を制作しましたが、私は当事者、つまりアフリカ系アメリカ人ではないから、アンビバレンスとそれが生み出すものの探求だったのです。部外者あるいはネイティブとしての私の立場によって、このアンビバレントなポジションが構造となると思います。というのも、私はカンフー映画を観るのと同じように、ブラックスプロイテーション映画を観て育ったから、ポップカルチャーという意味では、我々は皆、ある程度は楽しんでいて、その結果汚染されていて、そして、お互いが結びついているのです。
アイザック・ジュリアン 『Ten Thousand Waves』についての考察
文/ 高士明(ガオ・シーミン) はこちら。
アイザック・ジュリアン インタビュー
グローバルではなく、ローカルを繋げて
I. 奇跡とまごう符牒 | II. 世界と故郷 | III. 人を見る目 »
